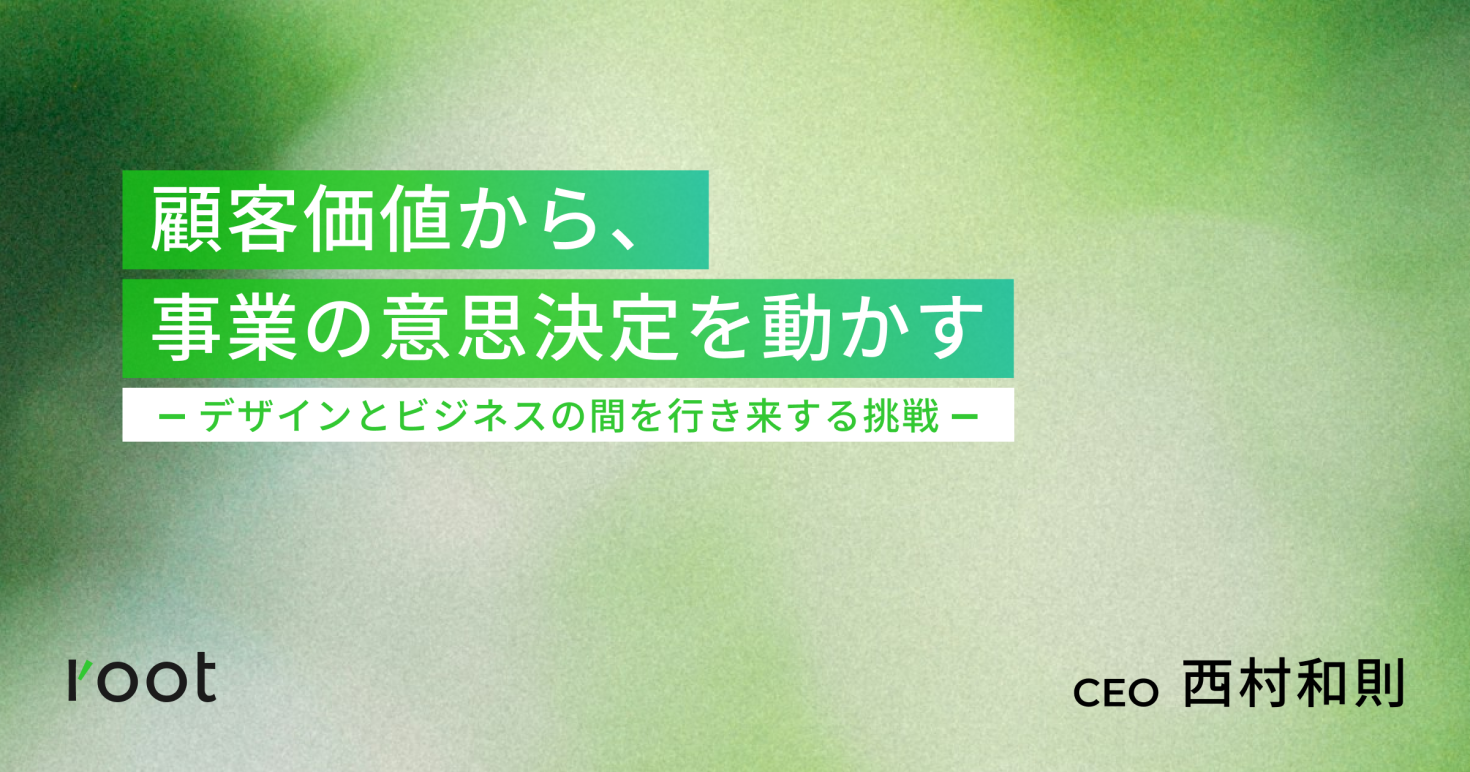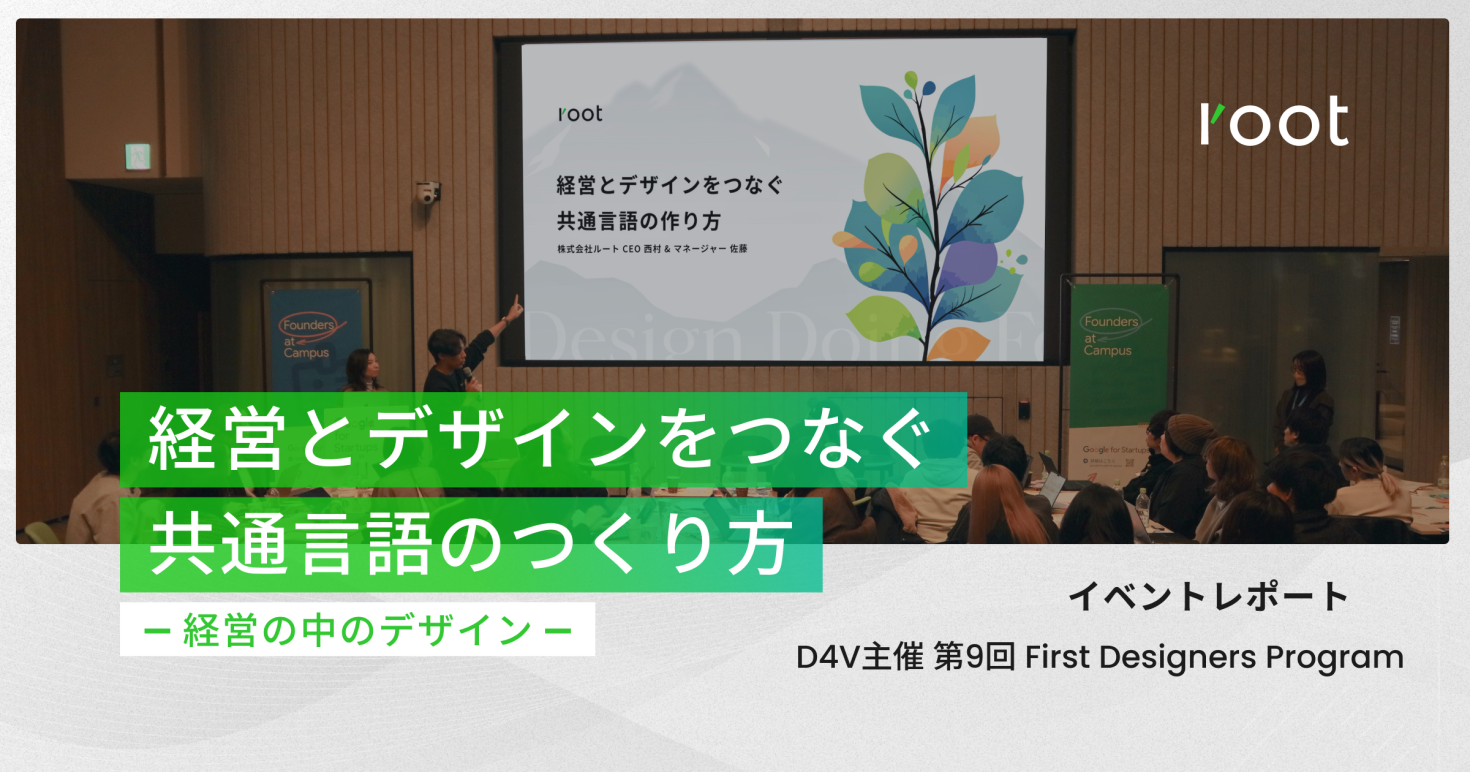- date
- 2025.07.14
AI時代におけるデザイナーのアウトカム志向と、AIと共創し組織知を高めるこれからの組織づくり〜AI時代の価値をつくるデザインとは?rootラジオVol.2〜
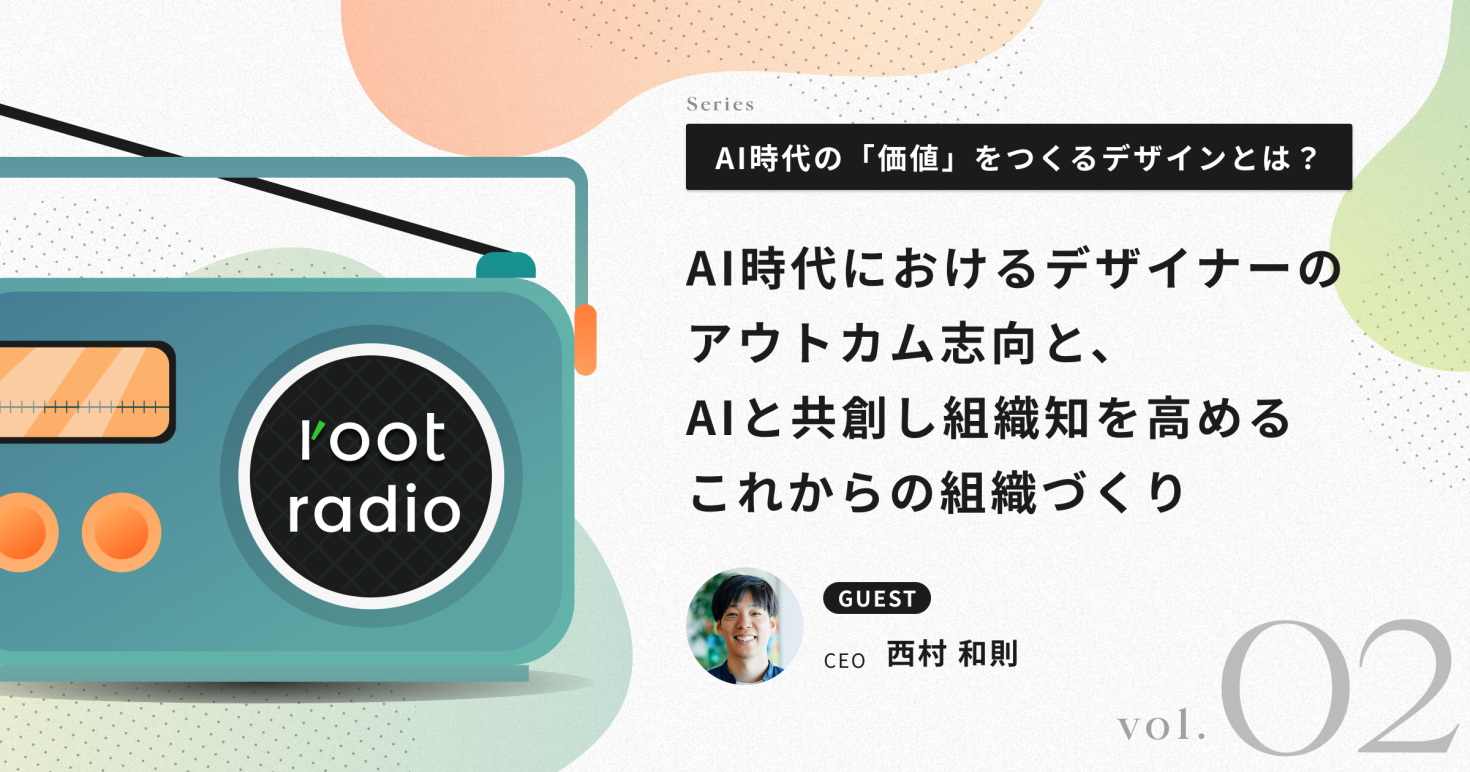
こんにちは!root採用広報担当です。
私たちは「Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜」をビジョンに、組織の右腕として、共に事業価値を創り、育むデザインパートナーです。
rootのデザイン支援モデルは、クライアントワークを通じ支援する組織・事業に対して共に事業価値を創り、育むための支援体系を構築しています。
事業の立ち上がりや成長段階に関わることの多いrootだからこそ、事業の形がまだ定まっていないフェーズから、本来あるべき事業価値の創造を共に行い組織と事業の成長を目指しています。
目次
rootラジオとは?
この度、社内で始めたrootラジオの放送内容を、ブログの連載企画として記事化することになりました。
冒頭で記載の通り、rootは、クライアント組織の右腕となるデザインパートナーとして、事業価値を創り・育んでいる中、
”rootラジオ”では、rootがクライアント組織の右腕となるデザインパートナーとして目指すことや、そのプロセスで起きるあれこれを、毎回トークテーマの中からゲスト(社内メンバー)とゆるく語り、その内容を社内で放送することで、それぞれに問いを立てていこうという企画になります。
また、rootはハイブリッド組織であり、現在は、オフィスでのコミュニケーションや関係値構築をセットで組織づくりを進めているフェーズです。
業務委託(rootでは、コラボレーターと呼んでいます)の方々はリモートのジョインが中心になるので、今社内でホットな情報や、組織の理解を深めてもらうためにも、ぜひ、聴いてもらればなと始めた放送でもあります。
ラジオで出てくる「問い」をぜひ、社内の皆が現場や日々の中で、引き続き考えたり、皆で話したり考えてほしいと考えています!
当面は3つのシリーズを考えており、直近はシリーズ1「AI時代の「価値」をつくるデザインとは?」について、前半と後半のコーナーにわけてお話ししていきます。
前半コーナーでは、”AIxサービス・価値づくり視点” について。
後半コーナーでは、”AIxキャリアやはたらき方”について、話していくことを企画しています。
前半、後半の最初では、15個ほどあるトークテーマからルーレットを回し、
その場で決まったテーマからお話ししていく企画になっています。
今回のゲスト紹介
今回は、ラジオ放送の第2回と第3回の様子をまとめて記事にしていきます。
どちらもゲストにはroot CEOの 西村を迎えお送りしました。
(本ラジオのパーソナリティは 、サービスディベロップメント兼HR・コーポレートセクションの管掌ジェネラルマネージャーである籔田が担当)
では、rootラジオレポート Vol.2はこちらです!
AI時代におけるデザイナーの「アウトカム志向」の重要性、偶発的な学びを生む余白のつくり方、
AIと共創するために必要な「目的を理解するためにとるべきアクションや考えたか」や「組織知を高めていくこと」の考え方など、
rootの実践を通じたリアルな問いや視点が詰まった内容になっていますので、ぜひ、ご覧ください!
放送内容
第2回放送分より
テーマ1:デザインの成果って何?
籔田:単刀直入にですけれども、まずデザインの成果って何か。
rootでは、成果の視点/指標として、アウトカムとアウトプットの違いを定義していけるといいなと思ってるんですけど、どうですか?
西村: そうですね。クライアントからオーダーされる時にも、アウトカムを起点にしたオーダーが来る場合もあれば、アウトプットをオーダーされることもあるので、それによって向き合い方とか、捉え方が変わってくるのは、実際起こってるかなと思いますね。
デザイナーなので、アウトプットを求められる場面が多いのですが、その際にもアウトカムを意識して支援をするっていうのがrootのスタンスなのかなと思うので、そこは結構違いが出てくるところなのかなと感じています。
籔田: アウトカムっていうと、すごいダイレクトな結果や成果みたいなものをイメージするかもしれないんですけれども、変化のプロセスとかもアウトカムであるという風に私も思いますね。それが定量的なのか定性的なのかは別として。
西村: ですね。マネジメントをする視点だと、デザインはやっぱり定量評価が難しいところになるので、成果って言われた時に何を聞いてるのかみたいなところが結構判断が難しい。みんな悩んでるところだと思うんですけど。
そこで、まず僕がやってるのは、デザインの成果目標の前に、企業のオーナー側が何を成果として実現しようとしてるのかっていう、ここの理解を深めていくアプローチをすることを、特に重視してやってるところですかね。
籔田: デザインマネージャー、うちでいうとつまりクライアントのデザインディレクションに責任を持つロールですが、(デザインのQCDSに責任を持っている)いわゆるrootが支援するプロジェクトチームのオーナーをするロール(PdMやCxO)は、
自身が相対するクライアント側のPdMやファウンダー、ボードメンバーなどがいて、その方々は皆どのレイヤーであっても、それぞれその人が持っている事業の成果や目標・目的というものがちゃんとそこにあるよということですよね。
西村: そうですね。基本的には事業なんで、KPIとか構造上落ちてる指標ってのは必ずあると思うので、それがまずどういった単位のもので見立てられているか。他にも目標や時間軸もありますよね。半期なのか1年なのかなど。これらによってもサイズや粒度が変わってくるので、この指標と時間軸、この両軸で見た上で、今、足元、目の前で求められてることが、どの単位で実現する成果なのかは、擦り合わせたり、認識を合わせていくというのは大事なのかなって思います。
テーマ2:自分の仕事に”余白”を残せてるか?偶発的な学びが未来をつくる?
籔田: 次のテーマに進めればと。まず、自分の仕事に余白を残せているかについて。例えば具体的にどんなことを余白ってイメージしますか?
西村: 遊びですかね。
籔田: 確かに。仕事に遊びを残せているかは大事ですね。
西村: 基本的に僕、偶発性大好き人間なんで、同じルーティーンを過ごしてると嫌になるんですよね(笑)
毎日同じ環境で同じサイクルで動いてるのが耐えられない。場所変えたりとか、はたらき方のリズムを変えたりとか、そういうのって動的にやっていて、そういう変化みたいなものを、楽しむとみたいなのは結構日常茶飯事かなっていう感じがしてますかね。
籔田: めっちゃわかります。そして西村さん、本当にそう。笑 私は若い頃、時間貧乏性だったんで、とりあえず予定が埋まってないと嫌でした。笑 でもある時、スケジュールに余白がないときに、お誘いを受けたことがあったんです。そのお誘いというのが、ずっとお会いしたかった方をご紹介頂けるという機会だったんですけど、その時は予定が詰め詰めで、お誘いを受けるチャンスを逃しそうになりました。
若かった当時は、あらゆるものにおいて、余白がないってこうなるんだって、すごい目の当たりにした経験だったのを覚えています。そこからは必ず、自分の人生も偶然性や、たまたまそうなって楽しむことなどは絶対に余白として置いておかないと、色々なものや人との出会いの数が減るなという風に思って。
西村: そうですね。それはすごいわかりますね。
籔田: 変化することは大切なことで、そんな時間を捻出したいからこそ、できるだけ効率的にしたいことやコストを割きたくないところはフロー化したり、毎日の決まったことはちゃんとルーチン化したいなと思いますね。AIもその延長線にあります。
西村: 逆に僕は余白ないタイミングを意図的に作るみたいなのは、ありますね。
余白があると、あるだけ遊んじゃって危ないんで。逆に(笑)
それを自分で課すというのはしてますね。
籔田: そうですね。余白を作るために、余白じゃないところをどういう風に作るのかみたいなところは大事ですよね。
第3回放送分より
テーマ3:AIが進化する中で、「何のために」を問う/考えることを日々できていますか?
籔田:まずは、今、西村さんが実際に支援に入ってるチームという単位から考えていければと思います。それぞれ何のために?って役割によってどこから考えるかが違ったりすると思うんですけど、西村さんが、チームのオーナーというかPMをしている中では、自分はどういったところから考えて、また、メンバーにはどう問うのか?工夫してる点からお話し頂けますか?
西村: 僕はお願いする側になることが多いので、自分がお願いすること自体のWhyを考えるみたいなことは当然多いです。デザイナーという職能もですが、仕事柄Howの話がやっぱり中心になりやすいというのはあるなと思っていて。
起点がそこから始まっても別にいいと思うんですけど、なぜそうなるのかっていうところをストーリとして考えていく機会とタイミングが必要なのかなと思っています。
そこを深掘りしないと、結局その中で議論してることや考えてることの方向性が、結局Howの話で終始してしまう。それだと、結果に繋がりづらかったり、何のためそれをやっているのかが分からず、手段が目的化するみたいなのは、そういうところから生まれてくることが割と多いかなっていう風には思っていますかね。
籔田:なるほどですねー。すごくわかりますね。さて、ここでリスナーの岸さんから質問を頂いていますので、読み上げます!
質問:「ストーリーで語るをもう少しわかりやすく言うとどういうことか教えてほしいです」
とのことです。
西村: キーワードになることとして、共感性があります。
相手へのメッセージを伝える際、タスクやアクションなどは、構造的に落とし込んでいけるものですよね。でも、それをなぜやるのか、どのようにやるのかみたいな話になった時に、現場がそれにどう向き合っていくか、どういう考え方でそれを扱っていくかは、情緒的な側面が入ってくると思っています。
その際に、なぜやるのかに対する共感性や、同意みたいなところがないと、なかなか引き上げていくのが難しいかなとと思います。
籔田:確かに誰かの目的は誰かの手段になったりしますよね。目的と手段って、その構造で階層になっていて、ツリーになってるので、何のためというのが、自分のやることから「すごく遠い何のために?」だと割とノイズになることもあると思うんですよね。
なので、本人にとって必要なWhyや何のために?なのか、認識を合わせながらやっていくっていうのが、マネジメントをする上でもすごく大事だったり、要点だったりするかなと思います。
西村: そうですね。任せられている役割や裁量など、そういったものと紐づいてくるっていう側面もあると思うので、まずは自分が実行できたり、意思決定できる範囲がどこなのかっていうのは、考えなきゃいけないところの1つにはなるのかなっていう風には思いますかね。
あとは、考えても結論が出ないことって結構あって、アクションを先に取るっていうのを結構大事にしてますかね。行動することで見えたり、分かることって結構あって、それをどう動かしていくかというのが結構大事かなって思います。
例えば、 クライアントと仕事をしてると、クライアント側の組織の問題からその場に決定する人がいない状況っていっぱい起こるんですよね。そういう状況の中で議論をしてても前に進まないものって結構あって。
そういう時に、1つの正解を当てに行くみたいな考え方がうまくいかない要因だと思っています。
布石を打つみたいな感じで、アクションをまずは取ることで、それが間違っててもいいので、それによって次の材料が出てきたりします。Whyを掘る・何のためにやってるのか?という、問いになるものが出すことができるかは結構大事かなと思っています。
籔田:そうですね。「何のために」がわからないと、取るアクションが無駄になってしまうとか、損をするみたいな考えの人もいたりすると思うんですけど、そうではないということですよね。それをするからこそ見えるものがあるというプロセスであるということですよね。
テーマ4:AIと共創していく上で、この先、「人」にはどんなケイパビリティが必要なのか?
籔田: さて、次はキャリアやはたらき方のテーマからですね。
AIと共創していく上で変わっていくケイパビリティと、価値を生み出すため、もしくは価値を提供するために変わらないケイパビリティ、そしてAIと共創していく上でプラスアルファ必要になるケイパビリティがあると思うんですけど、それぞれいかがでしょうか?
西村: AIの出来ることがものすごい増えていくことが前提になっているので、それを扱えるスキルセットは確実に必要になるだろうなと思っています。
現時点で見えてる範囲だと、言語化する能力や目的を伝える力はかなり問われてくると思います。
AI側も思考する力が出てくるのが前提になってくるので、単純に、伝えられる能力じゃなくて、Whyを伝えていくことが、AIにおいても重要になってきますよね。
文脈や背景を読み解いた上で、AIをどうはたらかせられるかが大事になるなと考えています。
籔田: そうですね。個人的には、HR領域や、エクスペリエンスデザインみたいな領域では、
組織全体の知能を高めていく設計をどうしていくか、(OI=Organization Intelligence)みたいな考え方)が、最近ホットかなと思います。
これからは個ではなく、この組織全体の知であるOIというものをどう高めていけるかみたいなことをHRとしてはどう設計できるか、デザインできるかみたいなことですね。
今後、個人の処理能力や思考能力はおそらくAIが担っていく。というかAIに負けちゃう。
それに対して、それらを集合させたり、その中の分散知をしっかりと育てていくための仕掛けをHRとして出来るかが大事だと考えています。
失敗をナレッジにしたり、そこからの学びを文化や仕組みにしていけるかというところで、組織の知性を高めるための、組織や人材マネジメントが重要になってくると思います。
西村: そのOIが浸透してる組織の状態の中では、AIは、どういう位置付けで活用されてたりとか、利用されてるようなイメージなんですか?
籔田: 当然、情報処理とかは、AIが速いわけなので、そこは、任せたいですよね。複雑な問題を解決してくれる相棒として成り立っていくわけではあるので、必要な人の数は減りますよね・・ただ、それらのデータやロジックを踏まえて、なぜそれをするのか、その違和感をどう感じるのか、またその上で、未来どうしていきたいのかを決めたりする。その感情や感覚、決断みたいなものはやっぱり人間じゃないですか。(価値観、倫理観、感情といったもの。)
ここが組織においても、この融合を実現して、形にしていくことが、有機的な組織だったり、次の多様性みたいな組織になっていくことは間違いないなと風に思っています。
リスナーからの声
籔田:Slack に届いた “生の声” をいくつかご紹介します!
🗣️「偶発的な出会いを逃さないように、能動的に余白を作っていきます!」
🗣️「ストーリーで語る例がリアルで腹落ちしました」
🗣️「OIの概念、多くのデザイナーに伝えたい!自分がつくることだけでなく、誰かとつくることに関心を持つ人が増えて、再現性を、チームで生み出せることをもっと当たり前にしたい!」
などなど
籔田:無事皆に聴いてもらえて何よりです〜笑
では、早いもので、そろそろ番組も終わりの時間となってきました。
rootラジオでの「問い」の時間は一旦ここまでですが、
明日以降、みんなが現場で色々な良い「問い」を持って、クライアントに向き合ったり、ステークホルダーに向き合ったりして欲しいなと思っております!
では、また来週この時間にお目にかかりたいと思います。さようなら!
おわりに
今回のrootラジオVol.2では、”AI時代の「価値」をつくるデザインとは?” シリーズとして、
第2回、第3回の放送内容をまとめ、4つのテーマを通じて議論を深めました。
次回のラジオ記事でも、AIを武器に、よりデザイン=顧客価値を創造することについて、また、その実現のための、はたらき方やキャリアについてお届けしますので、ぜひお楽しみに!!
rootでは共にビジョン実現できる仲間を探しています!
私たちは、「Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜」をビジョンに、様々なフェーズのクライアントの事業と組織の成長を共に実現するデザインパートナーです。
クライアント支援の立場から、個社での実践経験から得られたノウハウや課題を、組織的にナレッジとして束ね、支援する各社へ還元し、デザインの活動領域を個人から組織・事業へ広げ定着を促すことで、持続的な事業の成長にデザインが活かされる組織を増やしていきたいと思われる方!
共に、Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜を実現していきましょう!
ぜひ、ご興味ある方、一度カジュアルにお話ししませんか?ご連絡お待ちしています!
👇カジュアル面談はこちら
カジュアル面談をご希望の方はこちらよりエントリーください。
👇rootの採用情報はこちら
Vision・Mission・Valueやカルチャー、はたらいているメンバーの紹介など、充実したコンテンツで採用情報をお届けしますので、ぜひ、ご覧くださいませ!
👇root公式Xはこちら
プロダクトデザインや組織づくり、事業成長に関する知見やイベントをはじめとしたお知らせを発信しています。
ぜひ、フォローをお願いします!
(公式X)
We are hiring !
デザインの実践を個から組織・事業に活かすことで、より良い世界の実現を目指し、
組織の右腕として事業価値を共に創り・育むデザインパートナーチームを共につくっていきませんか?
クライアント支援の立場から、事業価値づくりにデザインが活かされる組織を増やしていくことにご興味のある方、ぜひ一度お話ししましょう!