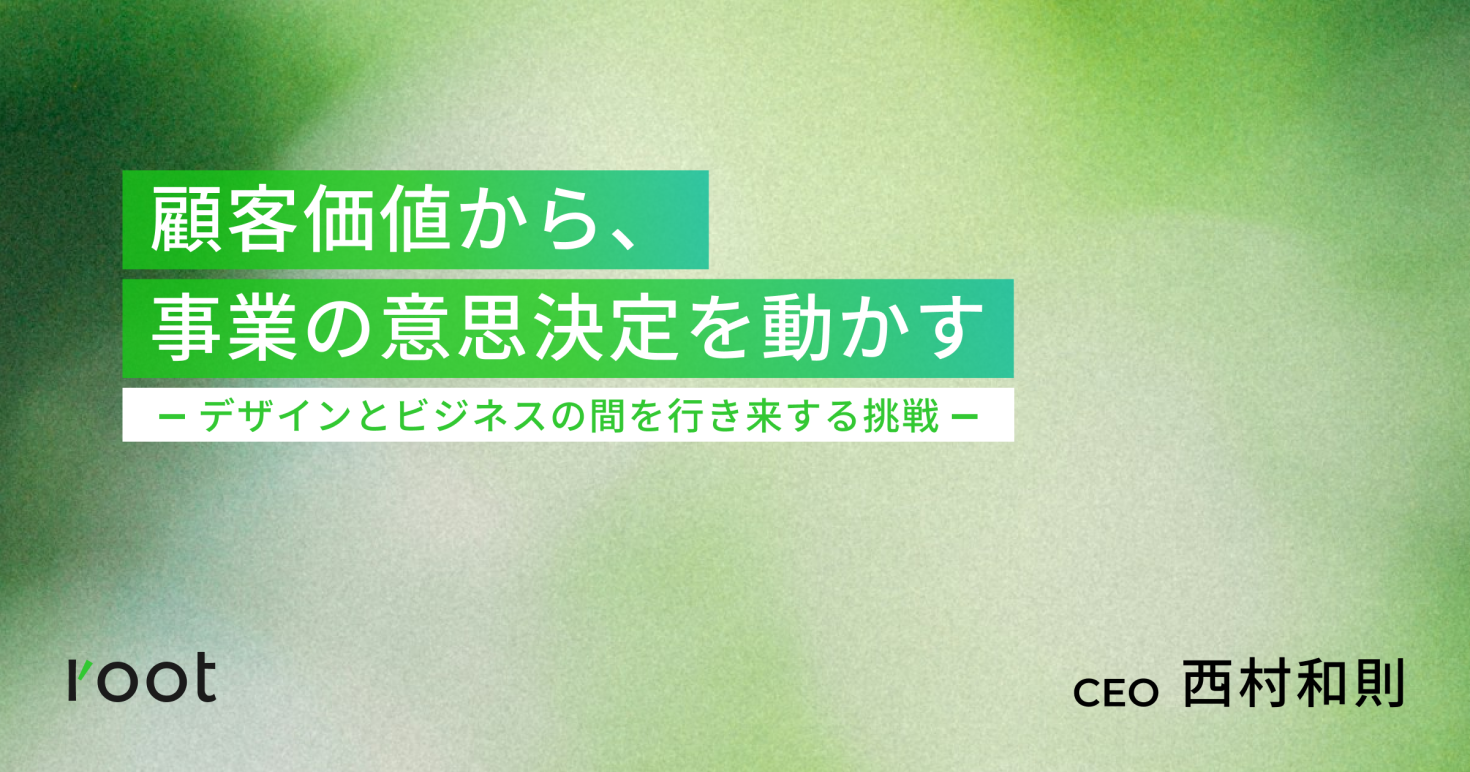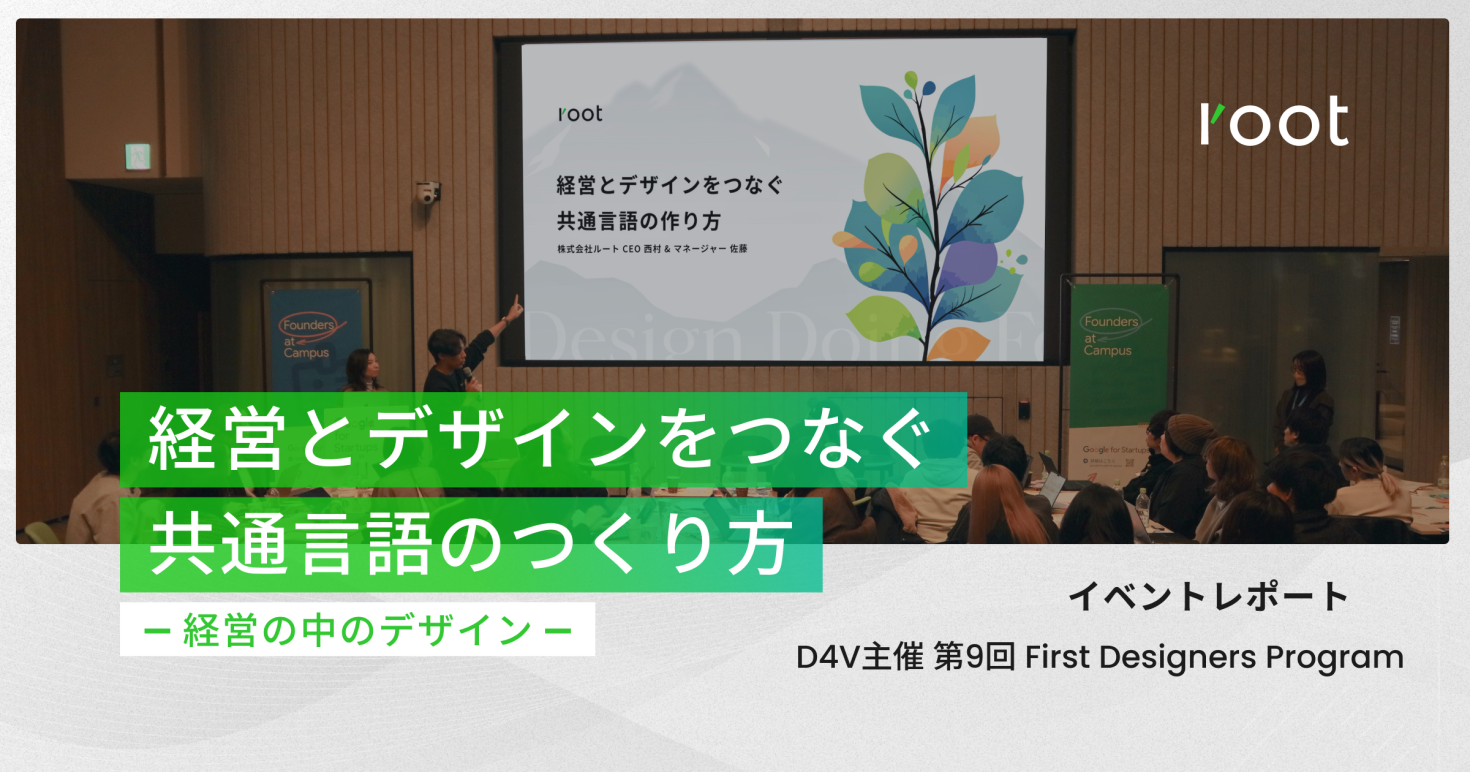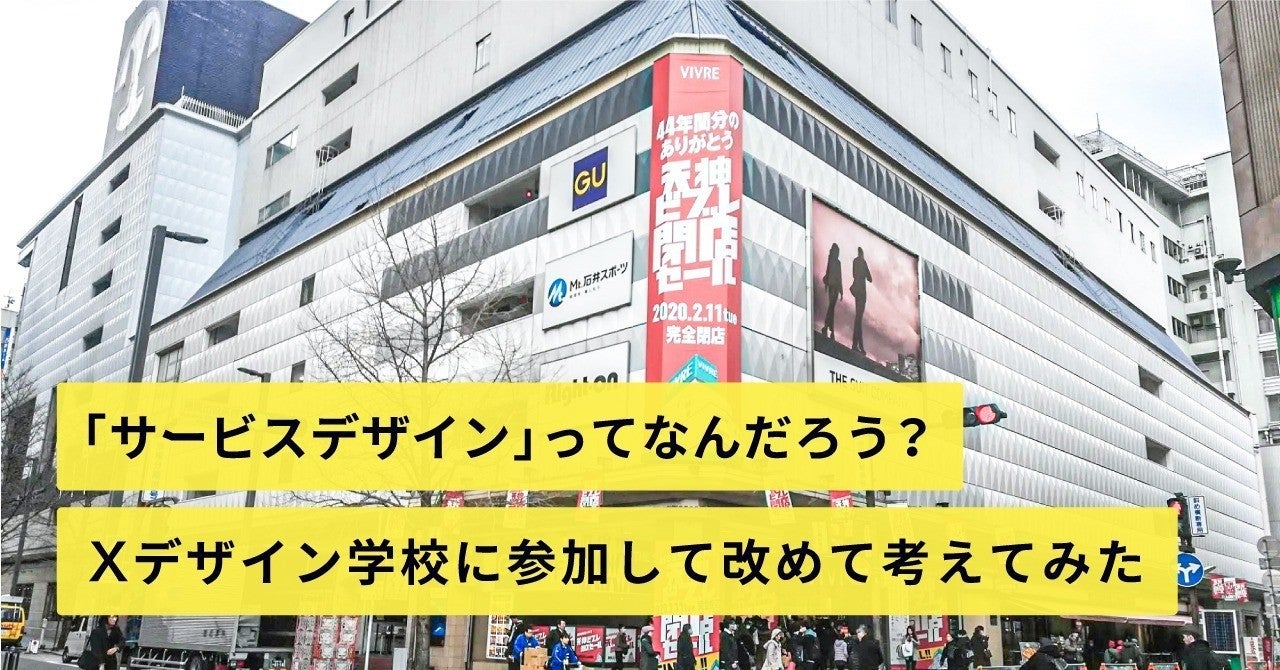- date
- 2025.09.10
コミュニケーションデザインとプロダクトデザインのマネジメントにおける共通項とデザインのアウトカム〜組織の右腕となるプロアクティブなデザインチームとは?rootラジオレポートVol.7〜

こんにちは!root採用広報担当です。
私たちは「Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜」をビジョンに、組織の右腕として、共に事業価値を創り、育むデザインパートナーです。
rootのデザイン支援モデルは、クライアントワークを通じ支援する組織・事業に対して共に事業価値を創り、育むための支援体系を構築しています。
事業の立ち上がりや成長段階に関わることの多いrootだからこそ、事業の形がまだ定まっていないフェーズから、本来あるべき事業価値の創造を共に行い組織と事業の成長を目指しています。
目次
rootラジオとは?
社内でオンエアしているrootラジオを、ブログの連載企画として記事化しています。
冒頭で記載の通り、rootは、クライアント組織の右腕となるデザインパートナーとして、事業価値を創り・育んでいる中、”rootラジオ”では、rootがクライアント組織の右腕となるデザインパートナーとして目指すことや、そのプロセスで起きるあれこれを、毎回トークテーマの中からゲスト(社内メンバー)とゆるく語り、その内容を社内で放送することで、それぞれに問いを立てていこうという企画になります。
また、rootはハイブリッド組織であり、現在は、オフィスでのコミュニケーションや関係値構築をセットで組織づくりを進めているフェーズです。
業務委託(rootでは、コラボレーターと呼んでいます)の方々はリモートのジョインが中心になるので、今社内でホットな情報や、組織の理解を深めてもらうためにも、ぜひ、聴いてもらえればなと始めた放送でもあります。
ラジオで出てくる「問い」をぜひ、社内の皆が現場や日々の中で、引き続き考えたり、皆で話したり考えてほしいと考えています!
今回のゲスト紹介
今回は、ラジオ放送の第10回と第11回の様子をまとめて記事にしていきます。
どちらもゲストにはコミュニケーションデザインセクションのマネージャー兼ディレクターのあさひくんを迎えお送りしました。
“`
旭 俊成(旭 としなり)
root コミュニケーションデザインセクション マネージャー /株式会社GORO 代表
大学在籍時にデジタルハリウッドに入学。rootでのインターン経験を経て、スタートアップにてプロダクトデザイン、マーケティング業務に従事。
より多様なプロジェクトを支援するため、株式会社GOROを設立。 デザイン・コミュニケーション領域でのプロダクト立ち上げや改善を支援。
rootでは、現在、コミュニケーションデザインセクションのマネージャー兼ディレクターとして、
事業マネジメントおよび、プロジェクト管理やディレクション業務に従事。
プロジェクトのクオリティ担保と、チーム全体の成果最大化に取り組んでいる。
デジタル領域を中心に、クリエイティブとビジネスをつなぐ役割から、
自らの意思で選択し、つくることの挑戦を通して、人や組織の可能性を広げ、挑戦が連鎖していくような環境をつくっていきたいと考えている。
“`
(本ラジオのパーソナリティは、サービスディベロップメント兼HR・コーポレートセクションの管掌ジェネラルマネージャーである籔田が担当しています!)
では、rootラジオレポートVol.7はこちらです!
「制約と創造性のバランス」「ディレクターの重要な役割」「ナレッジ化の工夫」「アウトカムの定義」など、 rootの実践を通じたリアルな問いや視点が詰まった内容になっていますので、ぜひ、ご覧ください!
放送内容
第10回放送分より
テーマ1:制約や納期といった条件がある中で、創造性をどう担保していますか?
籔田: 早速ルーレットをしていただきたいと思います!
旭: 1番です!
籔田: テーマは「制約や納期といった条件がある中で、創造性をどう担保していますか?」ですね。
最初に、rootでは、デザインパートナー事業において、プロダクトデザインプロジェクトとコミュニケーションデザイン(CD)プロジェクトの2つの領域があります。コミュニケーションデザインプロジェクトでは、クライアントのWebサイトの新規立ち上げといったWebデザイン、ホワイトペーパーや冊子などのグラフィックデザイン、また事業フェーズに応じたブランディングなどを扱っており、その性質から納品型のプロジェクトとして、クライアントを支援しています。 あさひくんには、CDセクションのマネージャー兼ディレクターとして、事業マネジメントや、プロジェクト管理・ディレクション業務を担ってもらっています。プロジェクトのQCDS を担保し、チーム全体の成果最大化、そして売り上げの責任までを担っているマネージャーです。
CDセクションでマネジメントをしていく中で、特に納期というのは大事な条件の1つですよね。
制約って他にもあると思うんですが、いつもどういう制約が多いなと感じますか?
旭: そうですね、おっしゃるように時間的な制約が一番多いですね。あとは、クライアントさんのサイト構築の環境における制約や、担当スタッフのリテラシーのグラデーションによる制約とかは発生するかなと思います。
籔田: なるほど。そういった中で、デザインチームとしての創造性をどう担保していますか?
旭: やっぱり各プロジェクトごとの力の入れどころを、最初の段階で見極めるようにしていて、必要にあわせて優先度をちゃんとつけて進行するところは選択しながらやってますね。
特に、クライアントとの間で、きちんとトレードオフの認識合わせをすることは重要だと思っていて、スケジュールがきついとか、これやっちゃうと溢れそうだなとか、そういう情報を隠さず、テーブルに上げて、一緒に話す。そこで状況を共有しながら最適解を共に描いていく。まさに共創の姿勢が大事かなと思っています。
籔田: 共創する中で、フラットにクライアントだからと言って遠慮しすぎてもいけないし、でもお客さんっていうことを忘れてもいけないっていう、この塩梅が大事ですよね。元々デザイナーやってる時から、そのバランス調整は上手だったんですか?あ、そう、前提としてあさひくんはもともとrootでデザイナーとしてインターンをしてた経験があり、そこからプロダクトデザイナーだけではなく、セールスやマーケ、そしてディレクター、マネージャーとキャリアを積んでこられています。
旭: いえ、全くそんなことはなくて!(笑)
当時プロダクトデザインをやってましたが、PdMの立場の人から「遅い」とか「時間かかりすぎなのに品質低い」とか言われてました。
今思うと、施策やプロジェクトの単位で重心を見極められてなかったんです。
色々な立場を経験したことで、相手の目標や成果、目指してることを知ることの大切さに気づきました。
籔田: あさひくんから、相手の立場や期待に応えたいという気持ちを強く感じるのですが、これは、昔から?
旭:全然そんなことなくて(笑) 僕はもともと体育会系の人間で、過去にかなり厳しいマネジメントをしていた時期がありました。営業のチームを4人ほど任されていて、「やると言ったらやる」という雰囲気で引っ張っていたんです。
ただ、正しいことを言ってもチームの行動につながらず、結局チームが炎上して崩壊してしまったんです。悔しくて泣いてしまったこともありました。シンプルに、「本人がやると言ったのに、なぜ、動かないんだろう?」とすごく悩みました。
籔田: 間違ったことは言っていないのに・・という葛藤ですね。確かに、相手が動かないと結果につながらないですもんね。
旭: そうなんです。その時に「正しいことを言うだけではダメなんだ」と痛感しました。自分の正義を曲げなければならないと感じ、とても辛かったですが、人、チームへの向き合い方や接し方を変えるきっかけになりました。
結果的に、その方が自分にとっても周囲にとっても幸せになれると学び、スタイルを大きく変えることができたと思います。
籔田:なるほど! 旭さんの今のスタイルは、そうした経験から生まれたものなんですね。皆からも声が挙がっていますが、痛みを伴う経験からでしか成長できないことがあるもの、ですよね。ええ話や!と西村さん(CEO)も言ってるね(笑)
リスナーからの質問への回答
籔田: リスナーから質問が来てますね!「そもそも、クライアントが求めている成果を理解するためにあさひくんが工夫していることはありますか?」
旭: 環境と関係性の2つをポイントに置いて考えています。環境という意味では、Slackのチャンネルでデザインの話だけをするチャンネルでは得られる情報に限界があるので、事業全体のやり取りが流れるチャンネルに入れてもらうようにしています。そうすることで、断片的ではなく、事業の動きをつかめるんです。
籔田: なるほど、環境と関係性の2つですね。リモートでクライアントワークをしていると、Slackのチャンネルをどう横断するかは本当に重要です。うちのメンバーでも、カレンダーやSlackを見にいって「何が起こっているのか」「どういう文脈で会話がされているのか」を積極的に追う人がいます。これによって、事業、相手の目標や責任が明瞭になってきますよね。あとは、情報を待つのではなく、自分から入り込んで得ていくことが必要ですよね。
旭: そうなんです。そして関係性の部分では、例えばPdMやマーケ担当など、窓口の人にとっての一次相談窓口になれる関係性を築くように心がけています。最初の相談がこちらに来るようになれば、相手の悩みや本当に求めていることが自然と入ってくる。そこが大事だと思っています。
籔田: 窓口になれるかどうかって、すごく大きいですね。相談の最初の矢面に立つことで、相手の期待や困りごとが見えてきますし、そこで得られた情報をどう自分の中で整理し、チームに還元できるかが鍵になりますね。結果的に、それがチーム全体の成果につながる理解へと変わっていくんだと思います。
テーマ2:ディレクターって色々やることはあるけど、何が一番重要な役割だと思いますか?
籔田: 次のテーマです〜「ディレクターって色々やることあるけど、何が一番重要だと思いますか?」
旭: 僕が大事にしてるのは、プロジェクトチームの社内外問わず全ての人にとって、「その人がいればなんとかなる」って思ってもらうことです。 属人化させたいわけではなくて、それがひいてはrootの旭として、という意味なんですけど。
籔田: 自分がディレクターの経験を重ねる中で、これが自分の大事なミッションだな!って気づいたんですか?
旭: そうですね。色々なプロジェクトをやらせてもらっている中で、クライアント先で管掌してくれる人の割合が増えれば増えるほど、社内のリソースを使ってることになります。それを減らすことで、クライアント内で、リソースを組織の別のところに使えたりするなと。
旭: お客さんのプロジェクトだと予算がある中でリソースを配分する必要があるので、そこは前提条件に置きつつ、お客さんの満足度とチームのバランスをどう取るかみたいなところを、ディレクターとしては考えなきゃいけないポイントとして捉えてます。
籔田: 制約条件がある中でやることが前提と思えるかって大事ですよね。その中でどう最大化するかを考えるのが大事です。「できない」と始めるのではなく、限られた条件の中で成果を出すことを考えるのが仕事だと思います。
旭: そうですね。制作側はどうしても期間にバッファーを持ちたくなりますが、チームで「どう取り組むか」を話せる文化が大切ですし、それをつくるのはディレクターの声かけ次第だなと思います。
リスナーからの質問への回答
籔田: リスナーからの質問です!「デザインをベースに色々な経験を積まれる中で、デザインマネージャーをしている理由は何ですか?」
旭:一つは、自分の経験をレバレッジさせられるというのが大きな理由です。 もう一つは、デザインの考え方や問題解決は色々な場面で活用できると思っていて、その幅広さに魅力を感じています。マーケティングの文脈にも使えますし、開発にも通じるところがあります。そういった意味で、デザインマネージャーという役割の広さや可能性を感じています。
籔田:なるほど!デザインは過去や課題からでなく、未来を描ける強みがありますよね。幅広く活用できる可能性は本当に大きいですよね。
第11回放送分より
テーマ3:クライアントとのプロジェクトに対して、「納品して終わり」ではなく、各プロジェクト後の学びやナレッジ化をチームにどう浸透させていますか?
籔田: 次のテーマです!「納品して終わり」ではなく、各プロジェクト後の学びやナレッジ化をチームにどう浸透させていますか?
前提として、私たちrootでは、CDを中心としたや納品型のプロジェクトを「単発のアウトプットを届ける場」ではなく、継続型のPDプロジェクトとあわせて、各社にデザインを法人格として浸透させていくことで、会社や組織全体の価値づくりを目指しています。
また、継続型のプロジェクトのご依頼や実績が多いrootではありますが、それだけではなく、例えばその先に、クライアントのインハウス組織が形成された後も、自社では解決できないデザインの専門性を求められるようなご依頼をいただくことで、持続可能な関係性を築いていきたいと考えており、現在継続型のPDプロジェクトとあわせて注力しているサービスでもあります。
そんなCDを中心とした納品型のプロジェクトで、どうチームのナレッジ化をしていますか?というテーマですね。
旭: やっぱり難しいなって思うのは、日々皆が情報に溢れた中で生きているので、ナレッジをチームの学びにする時に、違った体験にしていかないと記憶に残らないなと思ったりしてます。数と質の部分で、数をやり続けるとか伝え続けるのは、リーダーとかマネージャーの立場からすると大事なんだろうなと。
また、それぞれが自分でやってみることが大事だなと思っています。自分ごと化してもらうためにです。
例えば、ディレクター間では週次で定例MTGをしていてプロジェクトの進捗を聞くのですが、そこで新しくトライしたことありますか?みたいな軽い問いを投げたりして引き出しています。rootの別プロジェクトでやってみたり、社内でやってみたりしてもらっています。
あとは、ぼく自身もやってみる、を大事にしています。
籔田:最近、具体的にどんなことをやってみましたか?
旭:あるクライアントが会議の最初に5分間の黙読タイムを設けていて、その間に議事録やFigmaを見てからスタートするという取り組みがあったんです。これによって前提の質問が減って、アジェンダがよりシャープになったので、rootの新しいプロジェクトのキックオフでも同じようにやってみました。メンバーに追体験をしてもらおうと思っています。
籔田: いいですね。経営者の方とかが多いと、どうしても事前に見ていただくとか、やっぱり厳しかったりする時もあるので、ブロックして時間を確保するとかは割と1つの方法ですよね。相手の役割や立場によって、非同期でいいことと、同期でやるべきことを見極めることが重要です。メンバーレベルでは非同期を推進すべきことでも、ボードメンバーや意思決定者に対しては、その場で集中して判断してもらう時間を作ることが、結果的に早い場合や、相手もそれを求めている場合もあります。
テーマに戻りますが、それぞれの経験が共有されることで、他のディレクターが「実際にやってみる」という流れにつながるのはいいですね。自分で取り組んだことを持ち帰り、また次の場でシェアすれば、マネージャーの中で解として蓄積され、チーム全体のナレッジになります。さらに、自分の体験を伴うからこそ言語化や教えることもできる。まさにroot内でよく話題になる「手触り感」 ですね!
旭: そうですね。実際にやってみたことは、ただ知っているだけの情報よりもずっと血肉になります。だからこそ、ディレクター同士でのシェアや、クライアントの取り組みを持ち込むような動きはすごく価値があると感じています。
テーマ4:プロジェクトのチームマネジメントをする上で、納品完了をアウトカムとせずに、他にどんなアウトカムを定義していますか?
籔田: では、次のテーマにいきましょう!「プロジェクトのチームマネジメントをする上で、納品完了をアウトカムとせず、他にどんなアウトカムを定義していますか?」ディレクターとして、アウトプットだけではなく、アウトカムをどうチームへ落とし込んでいるかを聞かせてください!
旭: アウトカムの大きな部類としては大きく2種類あり、クライアントの売り上げを上げるか、経費を削減し、利益を上げる方向性か。 このどちらかの性質を持ってると思っていて、今回のプロジェクトがどっちの性質のものなのかというところから考えます。そこから、ブレイクダウンして、プロジェクトのゴールを設定しています。
籔田: プロダクトデザインのプロジェクトを担当するメンバーも多いので、少し具体的に聞いていきたいと思います。
例えば、売り上げUPを図る時は、チームでどういう指標を置くことが多いですか?
旭: ウェブサイトの立ち上げとか改善ですと、BtoBでしたらリードの顧客数を増やしたいというのがクライアントが求めること。この場合は、事業KPIでいくと、リードのお問い合わせ数とか資料ダウンロード数になってきますね。
籔田: では、経費を削減し、利益を上げる時はどんな指標を持つことが多いですか?
旭: 例えば、WordPressでサイトが運営されててサーバー費用がかかってるとか、外注費がかかっちゃってるという問題を、Studioに切り替え、運用設計することで月額◯十万円発生していた外注費を0にしたり、ウェブサイト運用を、社内スタッフのみで完結する形にしたり。そういったものをプロジェクトの目標に置いています。
籔田: 抽象的なゴールと、それをどう計測するかという指標をちゃんと連動させて往復するということをみんなにも意識してほしいし、マネージャーはそれをした上で渡すっていうことが大事ですよね!
あとは、CDで納品するプロジェクトはアウトプットやアウトカムがわかりやすいことや、納期というラインがあることが特徴的ですよね。そこは継続型のPDプロジェクトとは違った緊張感がありますね。
リスナーからの質問への回答
籔田:質問が来ています!「逆に旭さんは継続型のPDプロジェクトをやっている時と、CDに多い納品型のプロジェクトでは、どういう違いがあると考えていますか?また、継続型のPDプロジェクトでもこう考えれば同じだよね、等共通項があれば聞きたいです」
旭: 抽象的ではありますが、継続型のプロダクト開発も断続的にプロジェクトが起きて並走していると捉えています。同じように複数ラインを動かす感覚で取り組んでいます。 ただ、継続型のPDプロジェクトはアウトカムの設定が難しい場面もあるので、そこはお客さんとのすり合わせが欠かせません。
籔田: あさひくんはその「すり合わせ」が上手ですよね。打ち合わせで論点を整理してくれるし、相手の頭の中とこちらの認識を合わせる自分なりのナレッジを持っていると思います。ぜひ、それをブログで発信してほしい。チーム全体の資産になるはず。自分にとっては当たり前でも、他の人にとっては新しい学びになることって多いよね。
旭: 確かに。今あらためて考えてたのですが、納品型のプロジェクトの場合はあらかじめ要件や予算が固まっていますが、継続型のPDプロジェクトは一緒にゴールをつくっていく、というか変化していきます。時間の経過とともに、関係性もでき、お客さんのここから理解してほしいという期待内容が変化していきます。その中でこちらに「整理してほしい」と期待される部分も増えてくる中で、どう提案をしていったり、情報を得ていくかかなと。
籔田: そうですね。継続型のPDプロジェクトでは相手の期待値が変化するからこそ、ゴールを達成すればまた変わっていくし、途中で変わることもある。 加えて、クライアントの期待をどうキャッチアップできているかが重要です。
最初より、このくらいはわかってほしい、このコンテクストでわかってほしい。そう思うのが人間であり、関係性。rootが価値づくりで相対するのは、人です。そして、これが人ができることでもあると思います。アウトカムや目標も、相手からではなくこちらから提案したり、そのための材料を得るためにどう動くか。どこをどう担えば、相手の目標や成果を達成できるかを考え組み立てていくことが重要ですね。
旭: 本当にそう思います。こちらが動いてキャッチアップしなければ、気づいた時には仕事を失っている可能性もある。人や信頼そのものが比較される領域だからこそ、圧倒的な当事者意識を持ち、相手にしっかり向き合える人が求められるのだと思います。
リスナーからの声
🗣️「制約や期待のズレによってチームで起きるギャップの乗り越え方はあるのか?」といった質問や、
🗣️「実現するフェーズで、課題を隠さずテーブルにあげて共創する、は確かに大事!」といった声。
🗣️「継続型のPDプロジェクトは相手の求めるアウトカムを動いてキャッチアップしないといつの間にか離れていってしまうなと再認識したので、あらためてアクションを省みたいです!」といった声。
が上がり、それぞれのパートでリアルタイムに色々な声が上がっていました。
籔田:さぁ、無事今回も皆に聴いてもらえて何よりです〜笑
では、早いもので、そろそろ番組も終わりの時間となってきました。
rootラジオでの「問い」の時間は一旦ここまでですが、
明日以降、みんなが現場で色々な良い「問い」を持って、クライアントに向き合ったり、ステークホルダーに向き合ったりして欲しいなと思っております!
では、また来週この時間にお目にかかりたいと思います。さようなら!
おわりに
今回のrootラジオVol.7では、「組織の右腕となるプロアクティブなデザインチームとは?」シリーズとして、第10回、第11回の放送内容をまとめ、4つのテーマを通じて議論を深めました。
制約がある中での創造性の担保、ディレクターに求められる役割、ナレッジ化の仕組みや工夫、そしてアウトカムの定義という、rootでのデザインマネージャー、ディレクターとして重要な視点が詰まった内容となりました。次回の記事は、番外編として「それぞれの設計「意図」を読み解き、 持続可能な未来の実現を考えた右腕デザイナーチームのEXPO2025研修をどどんと振り返り!」シリーズをお届けします。
rootではこの夏、EXPO2025の課題研修を実施してきました。万博のテーマから各国、各企業がどのような意図をもって、パビリオンや施設の設計(デザイン)をしているのかを、事前仮説、現地観察、再解釈のプロセスで読み解きました。
その社外研修を通じて得た学びをチーム内で循環させながら、デザイナーとして未来にどう向き合いたいと考えたのか、研修の様子をお伝えしていきます。ぜひお楽しみに!!
rootでは共にビジョン実現できる仲間を探しています!
私たちは、「Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜」をビジョンに、様々なフェーズのクライアントの事業と組織の成長を共に実現するデザインパートナーです。
クライアント支援の立場から、個社での実践経験から得られたノウハウや課題を、組織的にナレッジとして束ね、支援する各社へ還元し、デザインの活動領域を個人から組織・事業へ広げ定着を促すことで、持続的な事業の成長にデザインが活かされる組織を増やしていきたいと思われる方!
共に、Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜を実現していきましょう!
ぜひ、ご興味ある方、一度カジュアルにお話ししませんか?ご連絡お待ちしています!
👇カジュアル面談はこちら
カジュアル面談をご希望の方はこちらよりエントリーください。
👇rootの採用情報はこちら
Vision・Mission・Valueやカルチャー、はたらいているメンバーの紹介など、充実したコンテンツで採用情報をお届けしますので、ぜひ、ご覧くださいませ!
👇root公式Xはこちら
プロダクトデザインや組織づくり、事業成長に関する知見やイベントをはじめとしたお知らせを発信しています。
ぜひ、フォローをお願いします!
(公式X)
We are hiring !
デザインの実践を個から組織・事業に活かすことで、より良い世界の実現を目指し、
組織の右腕として事業価値を共に創り・育むデザインパートナーチームを共につくっていきませんか?
クライアント支援の立場から、事業価値づくりにデザインが活かされる組織を増やしていくことにご興味のある方、ぜひ一度お話ししましょう!