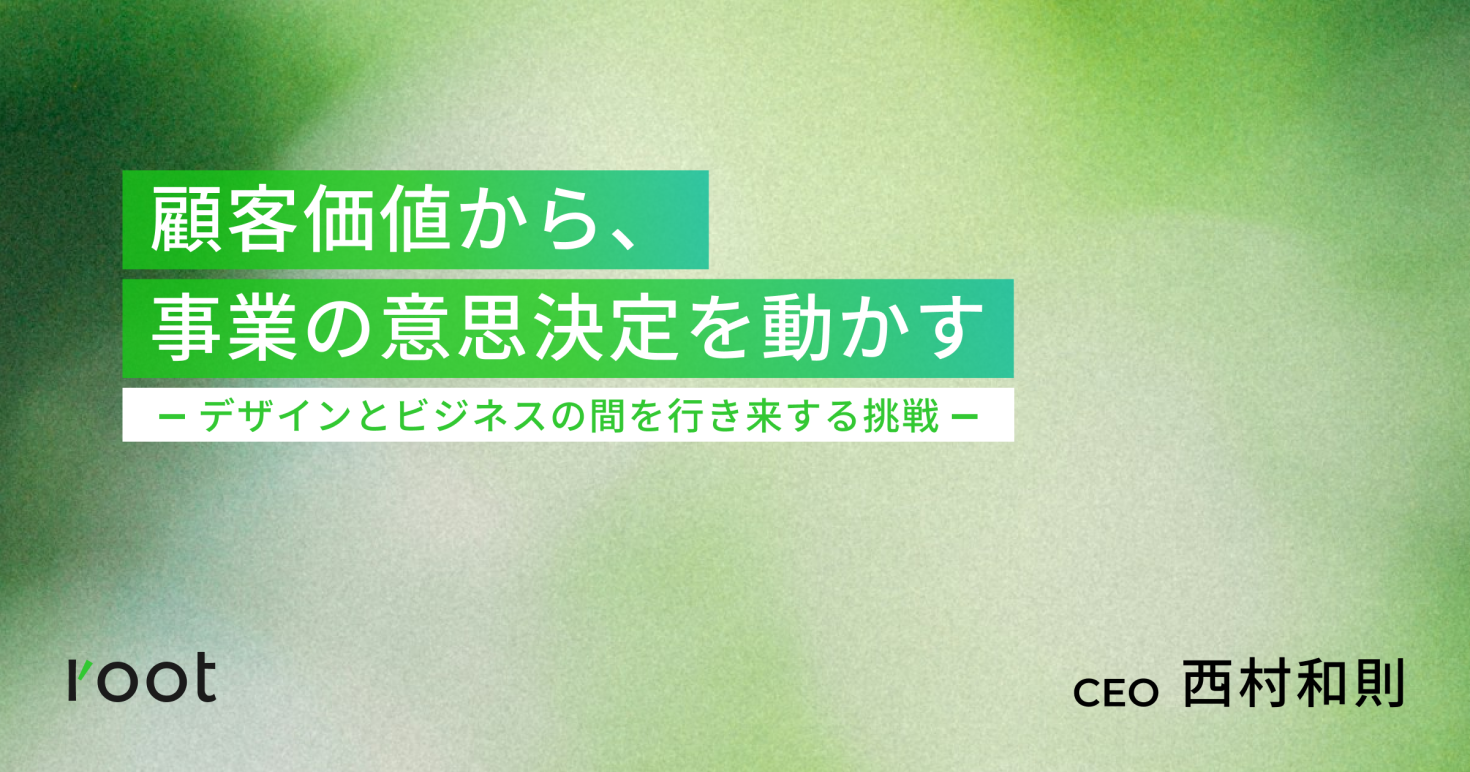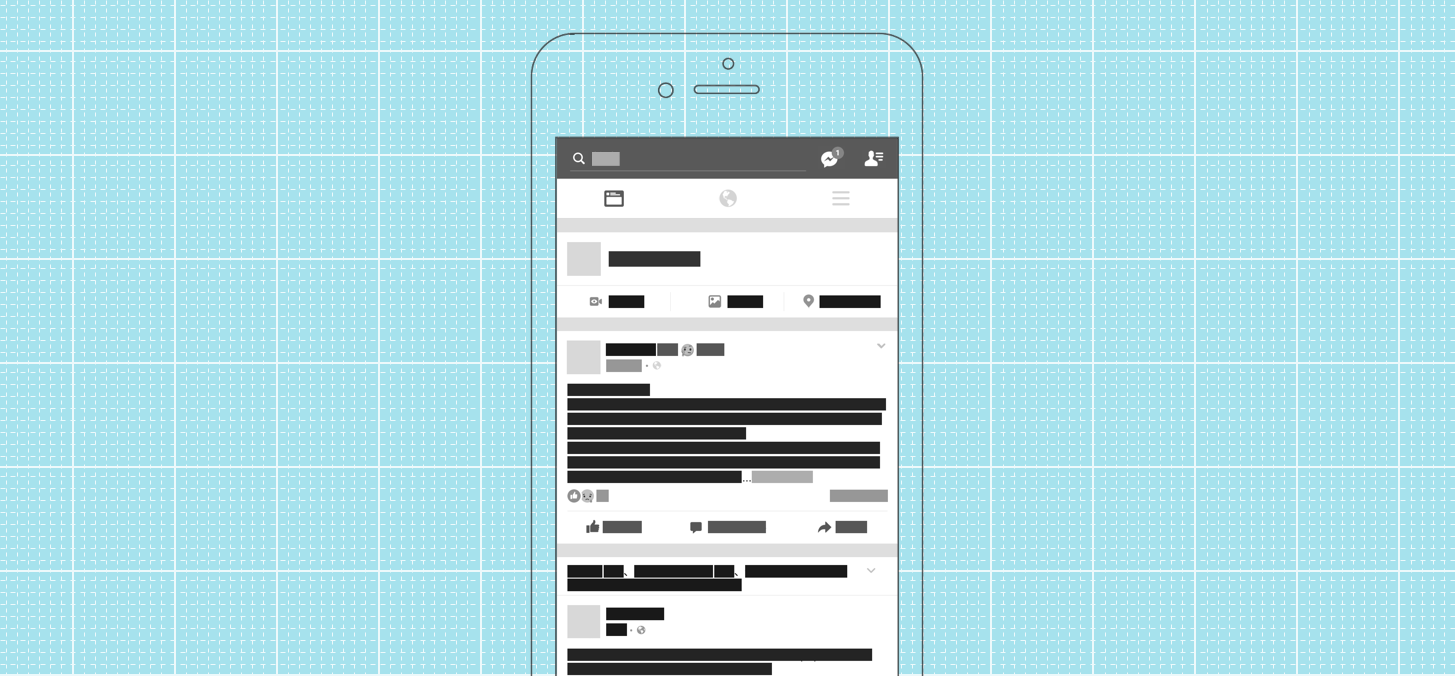- date
- 2021.12.03
事業立ち上げに伴走するデザイナーに求められる素養とは?
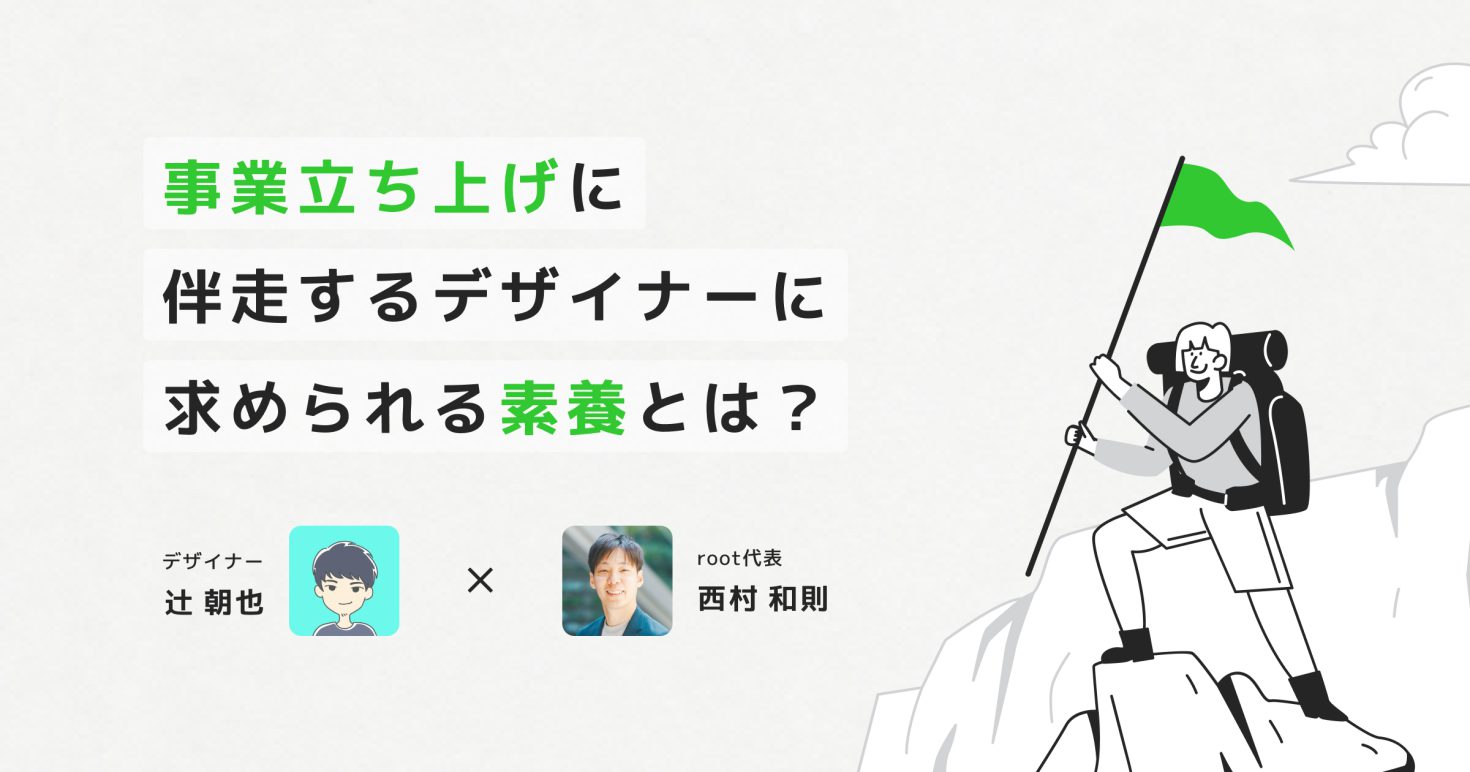
企業の規模に関わらず、新規事業を立ち上げる必要性が高まっている一方で、事業立ち上げフェーズに関わるデザイナーの数は不足しています。
事業の立ち上げフェーズという正解がない環境に身を置くデザイナーには、どのようなスキルやマインドセットが必要なのでしょうか。
起業家や事業責任者に伴走してきたデザイナーである辻朝也さんと、root代表の西村和則が事業立ち上げフェーズに関わるデザイナー像について語りました。
辻 朝也
2016年 クックパッド株式会社に新卒入社。レシピサービスで投稿・検索・会員領域を経験後、社内新規事業の立ち上げ、運用に従事。2021年 9月 株式会社YOUTRUSTに1人目のデザイナーとして入社。現在はデザイン基盤からサービスデザインまで広く関わっている。優しく寄り添うデザインが好き。
目次
デザイナーとして様々な事業の立ち上げに伴走
西村:辻さん、今日はよろしくお願いします。辻さんはどのような経歴でデザイナーとして活動されてきたのか、改めて教えていただけますか?
辻:私は大学でプロダクトデザインを学び、2016年にUI/UXデザイナーとしてクックパッド株式会社に入社しました。2年間はレシピサービスの改善などに携わっていましたが、3年目から「たのしいキッチンbycookpad」などの新規事業立ち上げに関わってきました。
また、副業として業務委託でも活動しており、本業も合わせると、ここ数年で複数の新規事業の立ち上げを経験してきました。
西村:本業でも副業でも、新規事業の立ち上げにデザイナーとして関わってきているんですね。
辻:rootも新規事業の立ち上げに関わるデザインチームという印象ですが、いつ頃から新規事業にデザインで関わっているのでしょうか?
西村:デザイン会社として活動するなかで、CrevoさんやFABRIC TOKYOさんの事業立ち上げフェーズに関わったことがきっかけですね。
この2社での事業立ち上げフェーズにおける経験から、違う分野のプロダクトであっても共通の課題を感じました。再現性を持って事業立ち上げに関わることができるのではと考えて、様々な事業に伴走するようになりました。
事業のフェーズごとの違いを経験して体に叩き込む
西村:私は試行錯誤しながら事業に伴走するデザイナーとして活動してきたのですが、辻さんはどうデザイナーとして事業成長に関わるように変化していったのでしょうか。
辻:事業の立ち上げフェーズの案件に複数関わったことで、勘所がわかるようになっていったと思います。おそらく、サービスの成長フェーズだけを経験していたら、事業立ち上げに関わるデザイナーに必要なスキルやマインドは育たなかったと思いますね。
西村:たしかに、立ち上げと成長だと必要とされることは異なりますからね。
辻:そうなんですよね。立ち上げフェーズは、不確定要素が非常に多い。そのなかで、デザインの正解なんてわからないので、ひとまず小さく作って壊してを繰り返します。成長フェーズは正解のパターンがある程度わかっているので、その正解に向かっていける。
「0→1」と「1→100」はまったくの別物で、そもそもの前提や勘所が違うことがわかるまでは苦労しました。立ち上げフェーズで何度も、何もないところからどういう目標に向かうのかを決めて、作ったり壊したりしながら進んでいく中で、前提が切り替わってきたと思います。
西村:その前提の違いを理解して対応できるかは、とても重要ですよね。立ち上げフェーズに貢献するデザイナーとして力をつけたいなら、まずは立ち上げフェーズでの経験値を増やして、この前提を身体に叩き込むのが大切だと思います。
辻:クックパッドの「たべドリ」というサービスのプロダクトオーナーが「同じ考えの延長には答えはないよね」という話をされていたのが印象に残っています。まさに立ち上げフェーズに必要な価値観だと感じました。
立ち上げフェーズに関わるデザイナーの動きは、アウトプットを作りながら見えない目標に向かって走っていくようなもの。新規事業を始めた当初は360度すべてに答えがある状態で、「見えている答えを探しに行く」という動き方ではないんですよね。
デザイナーがアウトプットを出して、方向を絞っていく。次の施策では、方向性を絞り込んだ、残りの可能性にフォーカスしてアウトプットする。そうやって「どちらの方向に向かって走るのか」という選択肢をできるだけ減らそう、と考えるのが重要だと思いました。
ここまで考えてアウトプットを重ねていくことができれば、事業全体を見ている起業家や事業責任者とも対等に話がしやすくなると考えています。
事業とデザインの目線を合わせて、併走する
西村:立ち上げフェーズでは、事業とデザインの目線をあわせるのも苦労しますよね。例えば、開発チームが先走って、機能ベース・開発ベースで進んでしまうパターンもあります。この場合、最終的に「このUI/UXは何のために作っているんだっけ」と、最終的な目的とずれる可能性がある。そうならないよう、定期的に軌道修正する必要があります。
辻:ありますね。
西村:起業家や事業責任者の思いや意思が強く、デザインチームが置き去りになるパターンもあります。
事業の立ち上げフェーズから関わるデザイナーにとって、どのように起業家や事業責任者とコミュニケーションするかは重要なことだと思いますが、辻さんはどのような工夫をしていますか?
辻:重視しているのは「目線合わせ」ですね。サービスの要件をまとめた「開発シート」を最初に作っておいて、それを適宜見ながら目線を確認するようにしています。
デザインチームが先行しがちな場合は、そもそも「デザインしない」。できるだけUIを作らずに既存ツールで検証した方が、「これだけ作ったのに違った」ということが起こりにくくなります。
また、起業家や事業責任者が先行しがちなら、デザインチームのパフォーマンスが落ちないよう、共通の指標を言語化してチームの戦力・団結力を上げるようにしています。
西村:起業家や事業責任者の目線を把握するのが不可欠かと思いますが、どうやってキャッチアップしていますか?
辻:直接聞きに行くのが、もっとも解像度が上がる方法だと思います。立ち上げフェーズのデザイナーは、待っているだけだと制作に近い工程しか任されません。優秀な起業家や事業責任者ほど自分でどんどん作業してしまいますからね。
デザインを任せてほしいなら、まずは自分から歩み寄る。そして何かを任されたら要望に応え、さらに期待されていることを把握した上でアウトプットを出すと、任される範囲が広がりやすくなります。
西村:私も起業家や事業責任者と関わる際には、まずは相手の考えを聞くようにしています。何を目指しているのかを知って、対等な立場で意見できるようになれば、ほとんどの現場はうまくいくのではないでしょうか。
辻:まず、歩み寄って、その上でデザイナーとしての価値を発揮できるといいですよね。どんなに優秀な起業家や事業責任者でも、ユーザー体験を正確に解釈できる人は少ないんです。提供すべき体験と実際のプロダクトとのギャップを埋める作業は非常に高度なので、専門家であるデザイナーがユーザー体験を軸に議論を進めていくのは大事だと思います。
西村:デザイナーは視覚的に表現して、考えを共有する能力に長けているので、説得力のある提案ができます。必要な事項を起業家や事業責任者、他のメンバーにわかりやすく示せるので、議論の調整役、旗振り役に向いていますよね。
立ち上げフェーズに関わるデザイナーに必要な経験や素養
西村:最近は、大企業で新規事業の立ち上げも増えています。立ち上げフェーズでやるべきことはスタートアップと共通するところが多いですが、違うのはビジョンの立て方です。
大企業では、会社の次の展開に必要だからという理由で新規事業が始まることが多く、熱意溢れる旗振り役が不在になりがちです。
目指す先が不明確だと、強いチームが形成できず進む方向性も定まりにくい。そのため、「チームとして旗をどこに立てるか」を引き出す、具体化するサポートを動きができるデザイナーがいるといいですよね。
辻:立ち上げフェーズに関わる際、デザイナーには「そもそも、このUIをなぜ作るのか」という問いを立てる精度の高さが重要だと思います。
ただ見た目を良くするのがデザインではないので、「このサービスには何が必要で、何が足りないのか」を正確に捉えていく力をつけていければ、事業の立ち上げフェーズにおいて価値を発揮できるようになるはず。
そのためにはまずは場数を踏むこと。業種やサービスの性質によっても勘所が違うので、まずは様々な事業立ち上げの現場を経験するのが大切ですね。
西村:なかなか新規事業の立ち上げフェーズに関わる機会を増やすことはできないので、場数を増やしたいデザイナーは辻さんのように副業で関わる機会をつくるというのはいいかもしれませんね。
辻:そうかもしれません。本来のデザイナーは枠組みの中で仕事をして評価されますが、立ち上げフェーズでは「いかにその枠を超えるか」で価値が生まれます。「役割の枠組みを超えられること」は事業立ち上げ期のデザイナーに必要な素養です。
その素養を磨くためには、関わる事業領域のリサーチに時間をかけて、どのデザイナーよりも詳しくなること。そして好奇心や学習意欲を持って物事を追求すること。「未知」を自分のものにすることを楽しめるデザイナーは、事業の立ち上げフェーズを経験することで大きく飛躍できるのではないでしょうか。
西村:辻さん、今回はありがとうございました!
We are hiring !
デザインの実践を個から組織・事業に活かすことで、より良い世界の実現を目指し、
組織の右腕として事業価値を共に創り・育むデザインパートナーチームを共につくっていきませんか?
クライアント支援の立場から、事業価値づくりにデザインが活かされる組織を増やしていくことにご興味のある方、ぜひ一度お話ししましょう!