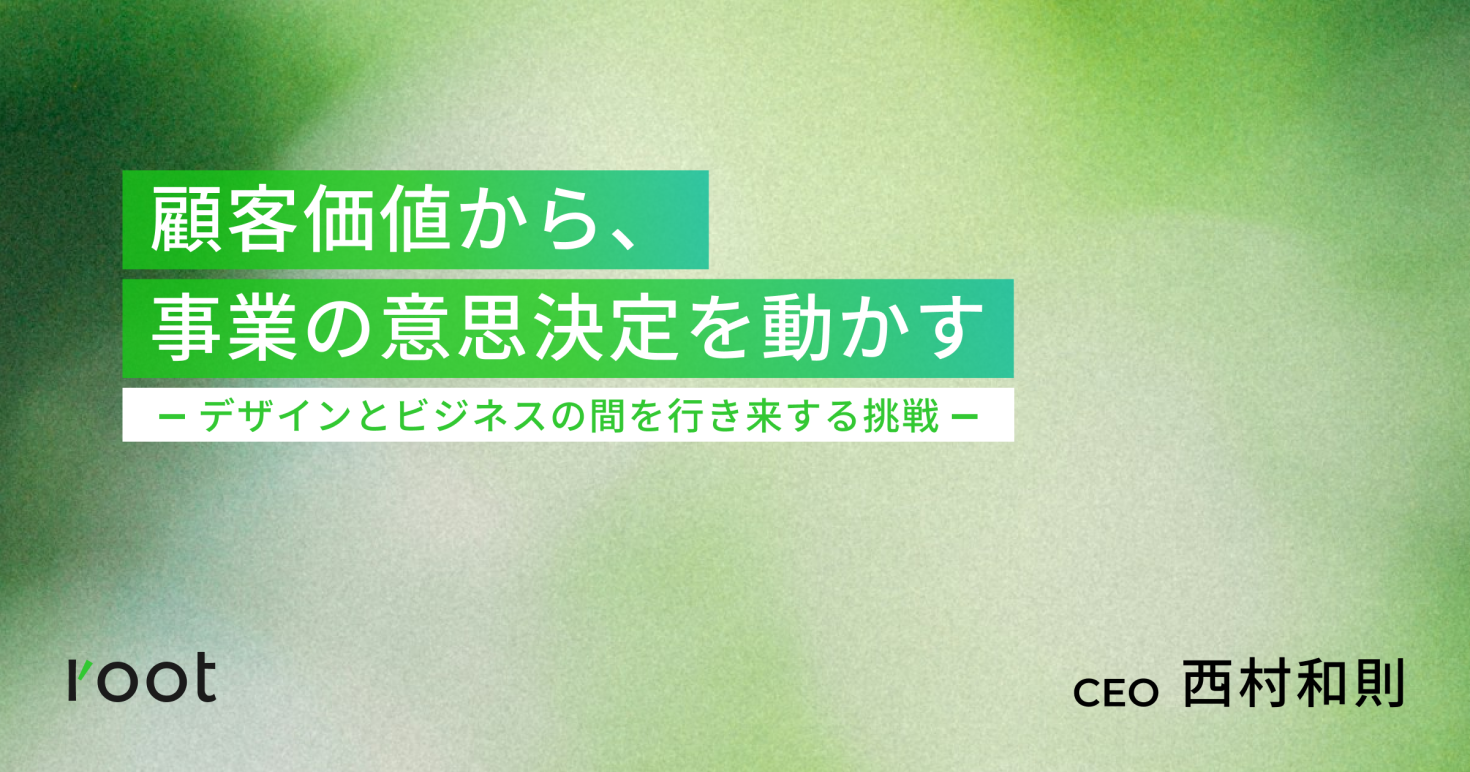- date
- 2025.07.09
「AI時代にPdMがデザインをマネジメントするべき理由と“好き”を深掘るビジョン 」〜AI時代の価値をつくるデザインとは?rootラジオVol.1 〜
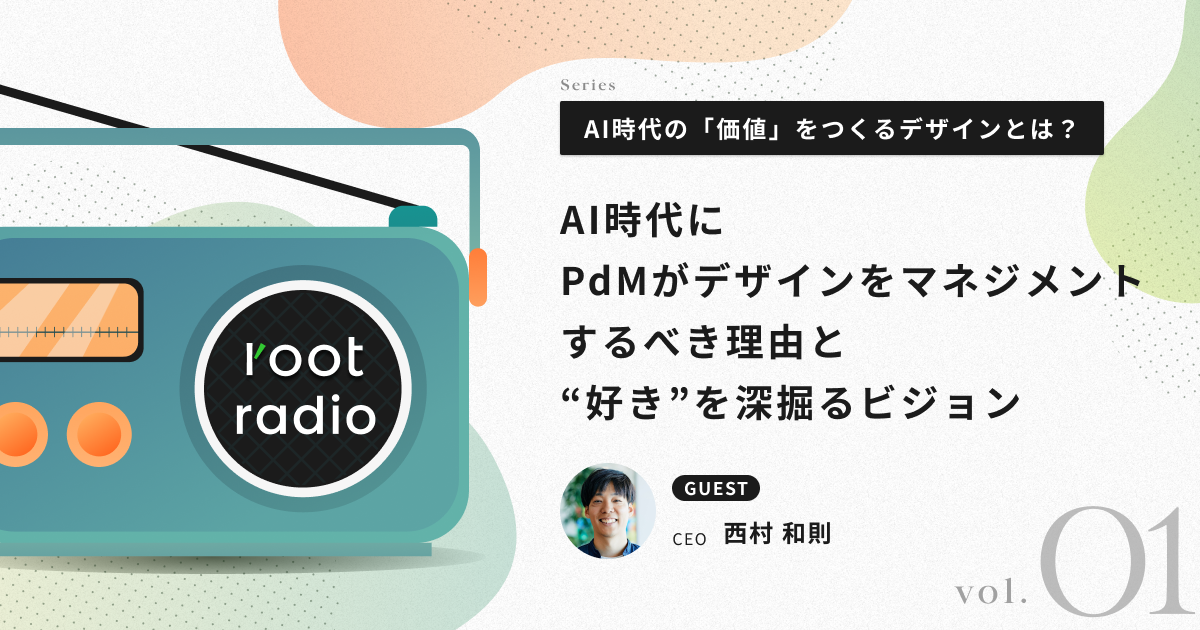
こんにちは!root採用広報担当です。
私たちは「Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜」をビジョンに、組織の右腕として、共に事業価値を創り、育むデザインパートナーです。
rootのデザイン支援モデルは、クライアントワークを通じ支援する組織・事業に対して共に事業価値を創り、育むための支援体系を構築しています。
事業の立ち上がりや成長段階に関わることの多いrootだからこそ、事業の形がまだ定まっていないフェーズから、本来あるべき事業価値の創造を共に行い組織と事業の成長を目指しています。
目次
rootラジオとは?
この度、社内で始めたrootラジオの放送内容を、ブログの連載企画として記事化することになりました。
冒頭で記載の通り、rootは、クライアント組織の右腕となるデザインパートナーとして、事業価値を創り・育んでいる中、
rootラジオでは、rootがクライアント組織の右腕となるデザインパートナーとして目指すことや、そのプロセスで起きるあれこれを、毎回トークテーマの中からゲスト(社内メンバー)とゆるく語り、その内容を社内で放送することで、それぞれ問いを立てていこうという企画になります。
また、rootは、ハイブリッド組織なので、現在は、オフィスでのコミュニケーションや関係値構築はセットで組織をつくっていっているフェーズです。
業務委託(rootでは、コラボレーターと呼んでいます)の方々はリモートのジョインが中心になるので、ぜひ、今社内でホットな情報や、組織の理解を深めてもらうためにも聴いてもらればなと始めた放送でもあります。
ラジオで出てくる「問い」をぜひ、社内の皆が現場や日々の中で、引き続き考えたり、皆で話したり考えてほしいと考えています!
当面は3つのシリーズを考えており、まずVol1~Vol.3では、シリーズ1「AI時代の「価値」をつくるデザインとは?」について、前半と後半のコーナーにわけてお話ししていきます
前半コーナーでは、”AIxサービス・価値づくり視点” について。
後半コーナーでは、”AIxキャリアやはたらき方”について、話していくことを企画しています。
前半、後半の最初では、15個ほどあるトークテーマからルーレットを回し、
その場で決まったテーマからお話ししていく企画になっています。
今回のゲスト紹介
初回となる今回のゲストにはroot CEOの 西村を迎えお送りしました。
(本ラジオのパーソナリティは 、サービスディベロップメント兼HR・コーポレートセクションの管掌ジェネラルマネージャーである籔田が担当)
では、記念すべきrootラジオ Vol.1の様子はこちらです!
AIが台頭する時代において、これからのPdMに求められる役割や、自身のビジョンについて考える機会として、ぜひ、ご覧ください!
放送内容
テーマ①:PdMがデザインするべき理由ってもう説明不要では?
籔田:では早速、前半パートは、「AI × サービス・価値づくり視点」に関する項目から、具体的なトークテーマを決めていただくために、西村さんにルーレットを回していただきます……
トークテーマは・・・・!「PdMがデザインするべき理由ってもう説明不要では?」について!
籔田:昨今、うちも今Qよりクライアントを支援する体制の中にPdMポジションを新設しましたが、そもそもPdMというポジションに何をお願いしていきたいとrootとして考えたかについてついて聞かせてください。
(PdM募集ポジション)
西村:プロダクトマネジメントの中には、デザインや顧客価値も当然対象として入っています。AIが入っていく前提の中で、サービスや商品が溢れている状況では、製品・サービスを差別化していく要素は体験や顧客価値に集約されてくると捉えています。
そのため、製品・サービス開発における「どんなことをどう設計していくか」のプライオリティが上がっていくと考えています。
UXという観点では、確実にプロダクトマネージャーはUXをマネジメントできないと、製品そのものの価値を顧客に提供することができません。ここを押さえることがすごく大事になってきます。
籔田:プロダクトの責任を取るPdMにとって、体験がほぼほぼの「価値」になってくるということでしょうか?
西村:そうですね。中心を占めてくるものになっていくと思います。
プロダクトマネージャーは開発ロードマップやプロダクトビジョンを描く立場なので、将来的にそのプロダクトがどうあるべきかを定める役割です。
その中で:
- 定量的に評価できるもの(ビジネス・事業指標)
- 定性的に評価できるもの(顧客価値・ニーズ)
この両方を押さえていくことがプロダクトマネージャーにより本質的に求められるものになってきます。
籔田:体験はアウトカムで、機能やUIは手段であるアウトプット。この違いを色々な職種や役割があるチーム内で認識を合わせるのは難しいものでしょうか?
西村:目指している状態やゴールを共通認識にするのは確かに難しいですね。「体験設計しましょう」と言われても、それぞれが想像しているものの尺度が違ったりします。
デザイナーが強いのは可視化できることです。今はAIを使うことで、企画・構想段階でもプロトタイプが作れるので、どういう体験になるのかを形にして共有できます。
ありたい状態をより早く具現化する力が重要で、作ることが目的ではなく、その先にあるアウトカム(成果)について議論し、目線を合わせて仕事をしていくことが必要です。
籔田:クライアントとの棲み分けや、AIの進化によって役割が変わっていく中で、どのような協業や共創ができていくと考えますか?
西村:支援する立場から見ると、本来クライアントの組織内で機能しているべきものがあります:
- プロダクトロードマップの策定
- 適切な意思決定の実行
- 開発サイクルの運営
しかし実際には、これらが機能していない会社の方が圧倒的に多いのが実態です。
デザインという役割やテリトリーで捉えるのではなく、事業の成長に貢献したいという共通の目的があるからこそ、役割を超えて必要なことをやっていく。
良いサービスで顧客に価値をちゃんと届けられる状態を作るために、役割を超えて取り組んでいくことが重要だと考えています。
籔田:ありがとうございます。現場で取り組んでいるメンバーにも参考になったのではないでしょうか!
もっと色々掘り下げたいところではありますが・・そろそろ次のパートの時間となりますので、後半パートに移っていきたいと思います。
後半パートは、「はたらき方・キャリア視点」の項目から、トークテーマを決めていただくために、再度西村さんにルーレットを回していただきます!
テーマ②:自分のビジョンってここから先なぜ大事なのか
籔田:さて、後半のテーマは・・「自分のビジョンってここから先なぜ大事なのか」について!
AIを武器にしていく中で、個々のビジョンがより大事になっていく時代に突入していると思うんですが、西村さんは最近、自分やメンバーのマネジメントでビジョンの大切さを感じた体験はあります?
西村: 定期的にAIに将来自分がどういうことをやりたいかを相談しています。笑
やりたいことを整理したり、深海に行くまでのプロセスを刻んだりとか。
ただ、「ビジョンを持ちなさい」って言われるとしんどいかもしれませんが、夢がある方がいいですよね。自己実現や他者のためになることって、人間が本能的に求めている欲求だと思うんです。
何かに貢献したいという欲求は誰でもあるはず。それを実現できないと思ってしまったら、いつまでも行動に移せない。僕は「どうやったらできるか」を毎日考えるタイプなので、面白いことを思いついたら、とにかくどうやってそれを実現するかを調べちゃいます。
デザイン会社の拡大について、規模や収益だけを求めていない人が業界には多いんです。じゃあ規模拡大の意味をどう捉えるかを、よくGPTと壁打ちしています。人に話すと「ああ言った、こう言った」みたいな迷いが出るので、まずGPTで整理してから人に話すのが最近のトレンドです。
籔田: まさにそこが重要で、「AIは目的達成のためのHowや解決方法を考えるのが得意」ですが、大事なのは
- どこがゴールなのか
- なんでそこに行きたいのか
- なぜそれをするのか
という自分なりの自己目的です。AIには「目的」(=意思)は考えられません。
自分のビジョンは、その人個人のバックボーンや歴史、価値観などが複雑に絡み合ったもの。これはAIには考えられないからこそ、ビジョンがキャリアで重要になってくる。
個人の能力はAIにどんどん淘汰されていく中で、自己目的化ができないと毎日同じことを繰り返すだけの生活になってしまう。
逆に「自分がなんでそれをしたいのか」「何を実現したいのか」が明確な人にとっては、めちゃめちゃワクワクする未来が待っている!!だからこそ、ビジョンがすごく大事になってきますよね。
籔田:さて、ここで、リスナーの佐藤さんから、質問を頂いていますので、読み上げます!
> 質問:
> 「目の前の誰かの役に立つことから絞れない、または広がらないデザイナーが多い。ピンが立つまでのプロセスで重要なことは?」
とのことです。
つまり、役に立ちたいという内的動機があるけれども、それを具体的にビジョンという自己実現したいことというところに持っていくには時間がかかるということ。
確かに、面接とか選考していても、職種によって絶対とは言わないですけど、受けることから始めがちなデザイナー人材には多いなというのは感じますね。西村さんは何かありますか。なぜそうなってしまうのかや、その旗が建つまでのプロセスで重要なことは何だと思いますか?
西村: 求められると役に立ちたいけど、自分自身の軸というか、ビジョンとして立てていかないといけないという人が多いということですよね。
籔田: そう、その通りです。
西村: これは自分自身で意思決定する機会を増やすというのがすごく大事だなと思っていて。
20代、結構しんどい思いをした方がいいというのはよく言われますよね。最近そういうことを言う人が増えたなと思っているんですけど。しんどいことに向き合ったときが一番自分が決断したりとか、意思決定する機会が多いなと思ったりします。
その機会を結構若い段階で得られているかって、結構重要だなと思っていて。自分で、最初起業するとか、創業して事業を自分で決めてやるみたいな決断、実際失敗をするという経験もしましたし。
人によって、見えるものとか得られたものが結構大きいなというふうに思っていて。それが結局は自分が背負える責任のサイズというか、そういうものを実感する機会だったのかなと思うんですよね。
当然、役に立ちたいとか貢献したいというのもあるんですけど、それ以上にやっぱりその先でその人が実現しようとしていることだったりだとか、それを本当に結果として出そうとなったら、それなりに自分も責任を背負わないとできないものって結構あるんだなと思います。
そういう、簡単に言うと覚悟、覚悟って言うとアレなんですけど、当事者意識みたいなものですよね。それを持てるかというのが結構大事だなと思ってますけどね。
籔田: そうですね。好きなことを見つけるとか見つけろとか、得意なものとかで能力伸ばせとか、それで勝負しろという抽象度で、結構大人たちは若手に言うこと多いと思うんですけど、そこをもうちょっと分解したら、好きなものの解像度をやっぱり上げるということだと思っていて、粗いなって思うんですよね。
で、まずそれを分解して細かくする。例えば誰かの役に立つこととか、ありがとうって言われることがすごく好きということからでも全然いいと思うんですけど。人に壁打ちとかしてもらってもいい。領域やセグメント、別にそのドメインとかじゃなくても全然いいんですよね。もうちょっとこう、好きというものの解像度を上げることによって、それをもっと深掘りするエネルギーも湧いてくると思ってて。
例えば私個人は、嫌いなことを聞かれる方が端的に答えられるんです。それ以外全部だいたい好きだと言えるのは、、色々なことに好奇心があるというのもそうですが、何か好きなもの、物事を見る時の好きの「視点」とか「角度」というのがあるから、何を見ても、どこなら興味を持てるか見つけられるというのがあると認識しています。
そして、しごとという価値提供では、西村さんがおっしゃるように、より責任を持つということって、スコープしていくということと結構付随してくると思うんですけど、そうなった時に、どれもいいけど、どこにスコープしたいんだっけ?って問う。こうして好きの解像度を上げるイメージです。
結局自分が何が好きなのかということを、どの解像度で理解できているかということは仕事、価値提供でもすごく重要だと思っていて。そうするとそこから自分で掘り下げていけるから、そこで、ここだったら自分が責任を持ってコミットできるなとか、責任もてるなって思えるところがみつかるというか。責任を持てば、やっぱり楽しいだけじゃないから、その楽しいだけじゃない中でそれをやりたいと思えるか、みたいなところが次のステップだと思うので、兎にも角にもまずはその好きの解像度を上げるということ。このステップが結構大事かなという風ふうには思います。
リスナーからの声
籔田:それでは最後に、Slack に届いた “生の声” をいくつかご紹介します!
🗣️「作業をそっちのけで楽しんでしまうくらいでしたー!!来週も楽しみにしてます👏👏」
🗣️「“体験” はいつも事後に観察されるものだから、“体験設計”という言葉がちょっと気持ち悪いと思っていたのですが、腑に落ちました。体験を設計するというよりは、あるべき体験を共有する営みに近いということですね」
🗣️「ビジョンを探すための自己理解がとても勉強になりました!好きなものにセグメントを切って自己理解を進めて、好きの解像度を上げていこうと思います!」
などなど
西村:放送中に思考のスイッチが入ったコメントが多いですね。沢山聴いてもらえて、僕らも励みになります(笑)
籔田:そうですね!初回、ドタバタでしたが、無事皆に聴いてもらえて何よりです〜笑
では、早いもので、そろそろ番組も終わりの時間となってきました。
rootラジオでの「問い」の時間は一旦ここまでですが、
明日以降、みんなが現場で色々な良い「問い」を持って、クライアントに向き合ったり、ステークホルダーに向き合ったりして欲しいなと思っております!
では、また来週この時間にお目にかかりたいと思います。さようなら!
おわりに
初回である今回は、ゲストにroot CEOの西村を迎え、AI時代における「価値」をつくるデザインについて深掘りしていきました。
ここからは、製品・サービスを差別化していく要素が体験や顧客価値に集約される中で、PdMが「デザイン」をマネジメントできないといけないこと。
また、「自分のビジョンはなぜ大切か」というテーマでは、AIが台頭する時代において、目的・意思を持つことが人には必要かつ重要になり、自身でビジョンを持つために、好きの解像度を上げ、意思決定の経験を増やすことで旗を立てる。それによってワクワクする未来を作っていくためのヒントが共有され、リスナーの皆さまにもキャリアを振り返る良い機会になったのではないでしょうか。
次回のラジオ記事でも、AIを武器に、よりデザイン=顧客価値を創造することについて、また、その実現のための、はたらき方やキャリアについてお届けしますので、ぜひお楽しみに!!
rootでは共にビジョン実現できる仲間を探しています!
私たちは、「Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜」をビジョンに、様々なフェーズのクライアントの事業と組織の成長を共に実現するデザインパートナーです。
クライアント支援の立場から、個社での実践経験から得られたノウハウや課題を、組織的にナレッジとして束ね、支援する各社へ還元し、デザインの活動領域を個人から組織・事業へ広げ定着を促すことで、持続的な事業の成長にデザインが活かされる組織を増やしていきたいと思われる方!
共に、Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜を実現していきましょう!
ぜひ、ご興味ある方、一度カジュアルにお話ししませんか?ご連絡お待ちしています!
👇カジュアル面談はこちら
カジュアル面談をご希望の方はこちらよりエントリーください。
👇rootの採用情報はこちら
Vision・Mission・Valueやカルチャー、はたらいているメンバーの紹介など、充実したコンテンツで採用情報をお届けしますので、ぜひ、ご覧くださいませ!
👇root公式Xはこちら
プロダクトデザインや組織づくり、事業成長に関する知見やイベントをはじめとしたお知らせを発信しています。
ぜひ、フォローをお願いします!
(公式X)
We are hiring !
デザインの実践を個から組織・事業に活かすことで、より良い世界の実現を目指し、
組織の右腕として事業価値を共に創り・育むデザインパートナーチームを共につくっていきませんか?
クライアント支援の立場から、事業価値づくりにデザインが活かされる組織を増やしていくことにご興味のある方、ぜひ一度お話ししましょう!