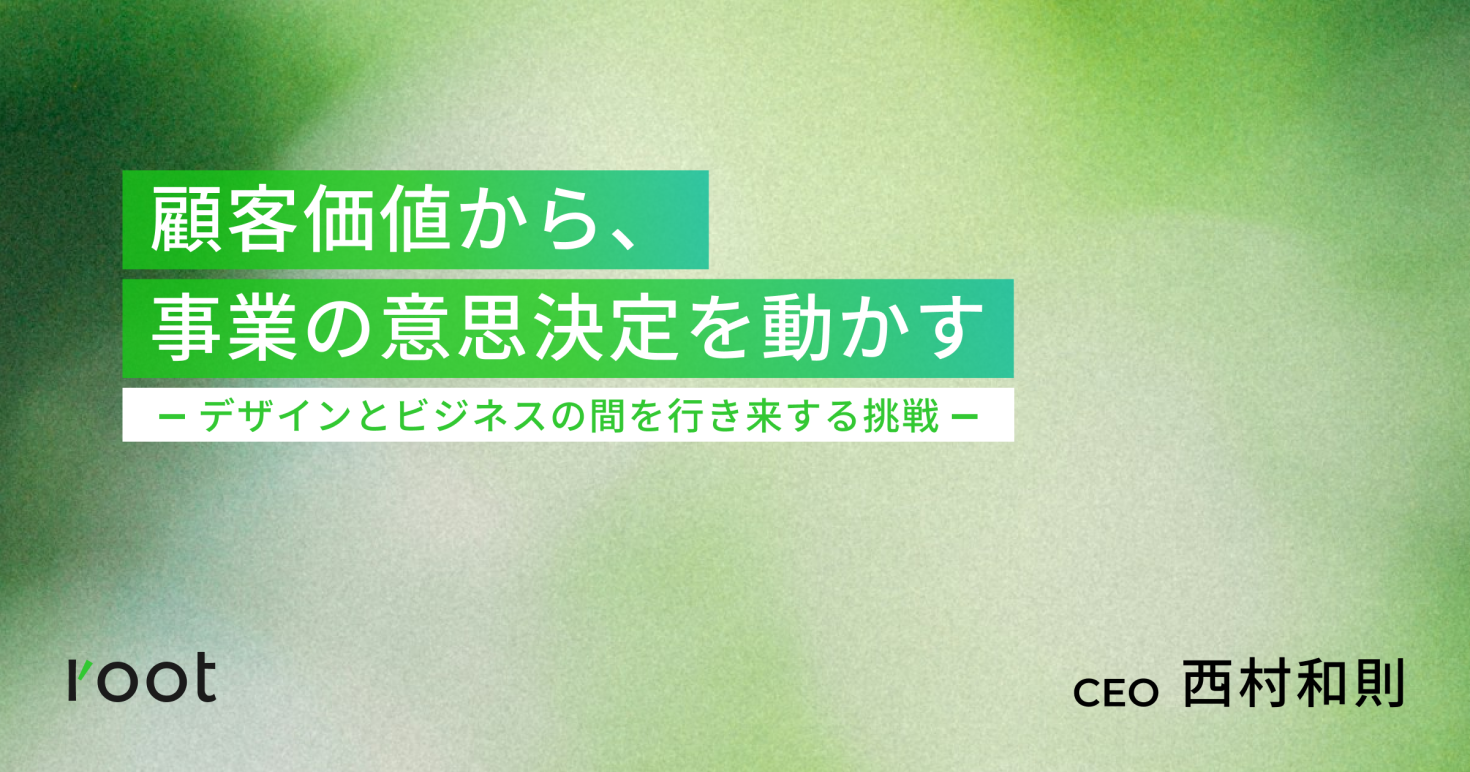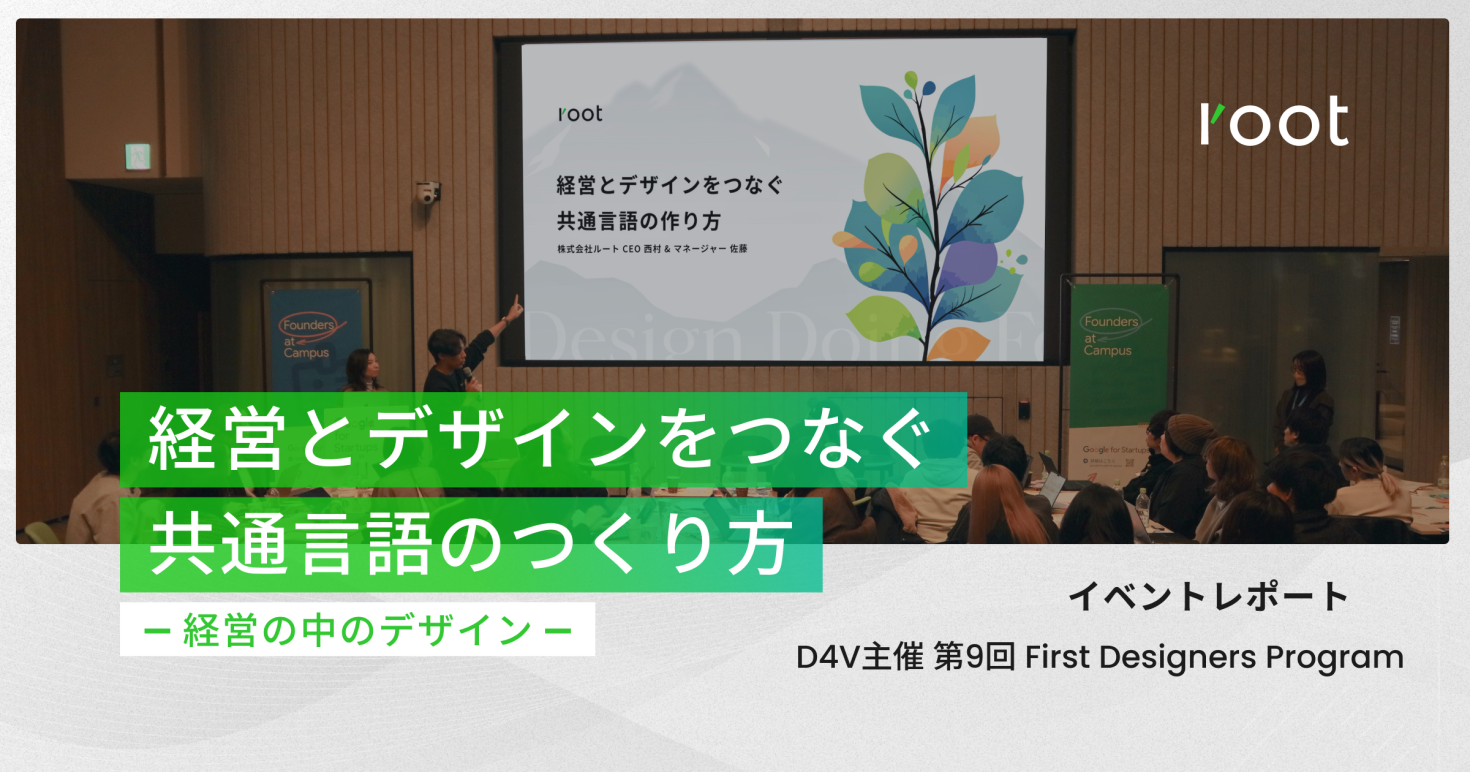- date
- 2025.07.30
事業と組織における短期的な成果の最大化と長期的な成長投資となるマネジメントのロードマップ〜マネジメント視点で考える事業価値に寄与するデザインとは?rootラジオレポートVol.3〜

こんにちは!root採用広報担当です。
私たちは「Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜」をビジョンに、組織の右腕として、共に事業価値を創り、育むデザインパートナーです。
rootのデザイン支援モデルは、クライアントワークを通じ支援する組織・事業に対して共に事業価値を創り、育むための支援体系を構築しています。
事業の立ち上がりや成長段階に関わることの多いrootだからこそ、事業の形がまだ定まっていないフェーズから、本来あるべき事業価値の創造を共に行い組織と事業の成長を目指しています。
目次
rootラジオとは?
この度、社内で始めたrootラジオの放送内容を、ブログの連載企画として記事化することになりました。
冒頭で記載の通り、rootは、クライアント組織の右腕となるデザインパートナーとして、事業価値を創り・育んでいる中、
”rootラジオ”では、rootがクライアント組織の右腕となるデザインパートナーとして目指すことや、そのプロセスで起きるあれこれを、毎回トークテーマの中からゲスト(社内メンバー)とゆるく語り、その内容を社内で放送することで、それぞれに問いを立てていこうという企画になります。
また、rootはハイブリッド組織であり、現在は、オフィスでのコミュニケーションや関係値構築をセットで組織づくりを進めているフェーズです。
業務委託(rootでは、コラボレーターと呼んでいます)の方々はリモートのジョインが中心になるので、今社内でホットな情報や、組織の理解を深めてもらうためにも、ぜひ、聴いてもらればなと始めた放送でもあります。
ラジオで出てくる「問い」をぜひ、社内の皆が現場や日々の中で、引き続き考えたり、皆で話したり考えてほしいと考えています!
当面は3つのシリーズを考えており、直近はシリーズ2「マネジメント視点で考える事業価値に寄与するデザインとは?」について、前半と後半のコーナーにわけてお話ししていきます。
前半コーナーでは、”事業マネジメント視点” について。
後半コーナーでは、”ピープルマネジメント視点”について、話していくことを企画しています。
前半、後半の最初では、10個ほどあるトークテーマからルーレットを回し、
その場で決まったテーマからお話ししていく企画になっています。
今回のゲスト紹介
今回は、ラジオ放送の第4回と第5回の様子をまとめて記事にしていきます。
どちらもゲストにはroot マネージャーのさとりこ(佐藤)と、サブマネージャーのへいへい(岸)を迎え、お送りしました。
(本ラジオのパーソナリティは 、サービスディベロップメント兼HR・コーポレートセクションの管掌ジェネラルマネージャーである籔田が担当)
では、rootラジオレポート Vol.3はこちらです!
事業マネジメントおよびピープルマネジメントの視点より、 クライアントとの関係値構築・ 事業の短期成果の創出と、長期的な成長への投資の両立・デザインリソースの最適配分・ メンバーの強みを活かすマネジメントなど、rootの実践を通じたリアルな問いや視点が詰まった内容になっていますので、ぜひ、ご覧ください!
放送内容
第4回放送分より
テーマ1:デザインマネージャーとして、またマネージャーとしてクライアントとの信頼関係をどう築いていますか?
籔田:デザインマネージャーとして、またはマネージャーとして、クライアントとの信頼関係をどう築いていますか?というテーマでお話ししていきたいと思います。
まず、どのようにして信頼関係を築いているか、必ずやっていることはありますか?
※rootでは、rootの事業責任(売上や利益目標)をもつのがマネージャー。
対クライアント支援における各種プロジェクトのQCDS責任(クライアントとの成果目標)をもつのがプロジェクトのオーナーとなるデザインマネージャーやPdMといったプロジェクトのオーナー(旧DPM)となっています。さとりこ:やはり相手のことを知ることではあるのですが、ただ知ればいいということではないと考えています。これが最初はつまずいたポイントでもあり、今絶賛鍛えているところです。
最初は結構むやみに雑談をしたり、知り合ったりという感じでやっていたんですけど、あまりうまくいかなかったんです。
籔田:ただ、「知る」。それだけではダメだったんですね
さとりこ:はい!相手のことを、必要な観点で知るということに気づきました。知ることについてもっと構造化して、PDCAを回さなければいけないと気づいた、ということです。
例えば、相手の役割・責任という要素、本人のケイパビリティやビジョン、これまでの経歴など、知る角度を増やしていくことで、相手のことをより多面的に知れるようになりました。
へいへい:僕も似たような話になってしまうんですけれども、最近変わったのは、相手にそもそも役割というものがあるということを改めて認識したことです。
これ、本当に当たり前のことだと思うんですが、その「役割」ならではの、やらねばならぬことが必ず存在している。相手がその役割から成果を出すために、自分たちが役にどう立てるか。
そのために、相手の立場や役割、状況から鑑みて、おそらくこの辺が欲しいのであろうというところを一生懸命考えたり、情報を集めたりすることを意識してやっています。
籔田:確かにそうだね。人と人という共通点では共通項が大きすぎていて、相手の「役割」から共通の目的を見つけにいくことが信頼関係を築く上で大事ですよね。
その共通の目的をどの粒度で思考し、アクションをとれるかというのは重要なポイントですね。
さとりこ:あと、Give精神という点から考えると、役割・責任から共通の目的を見つけた方が、Giveできることがたくさん見つかるようになりました。
コーヒーが好きとか、そういう雑談から得られる情報で相手に出来ることは限られていますが、共通の目的から自分の役割でできることが見つかると、それが大きなGiveになっていく。それが見つかった時は結構楽しい瞬間ですね。
籔田:へいへいが楽しいと感じるタイミングは、どんな時ですか?
へいへい:さとりこと重なってしまうんですが、ぼくも楽しいと感じるのは、役割という切り口から「相手を知ること」ですね。
役割というフィルターを通して相手を見ると、その人が日々関心の対象としていることに対して、解像度高く要求が見えてくると思います。
例えば、PMの方を例にすると、以前は相手の役割に対して「計画を前に進めるのでとても大変そうだな」と思っている側面がありました。ですが、役割という視点で見ると、その人が他の人からどういう期待をされているのか、個人目標を持っていたり、誰かに承認を求めに行ったり、「この人にこう思われたい」という個人的な気持ちがあることが見えてきたんですね。
人には色々な制約や人間関係がある中で、それでも「こうしたい」という思いがそれぞれあるはず。
表面的には開発の進捗だけを求めているように見えても、本当に欲しいものは別にある。
例えば「このプロジェクトの成功を通して、次はもっとこんなプロジェクトに挑戦できるようになりたい」といった個人的な目標があったりですね。
そうした「相手が真に求めていること」を見ようとして対話を進めると、お互いの中で「そうそう、これこれ」という瞬間が生まれる。お互いの利害が深く一致し、共通理解が生まれる時があるんです。
その時は、一緒に話していて良かったなと思える瞬間ですし、その構造を知ること自体が楽しいと感じるようになりましたね。
テーマ2:短期的な成果責任と長期的な個人の成長促進。マネージャーとしてどう両立させていく?
籔田:次は、短期的な成果責任と長期的な個人の成長促進、マネージャーとしてどう両立させていきますか、という問いです。
成果の責任を持ちながら、同時に個々人の成長を促進するという両面をどうやって両立させていますか?
へいへい:これ難しいのですが、本当にrootの中で口酸っぱく言われていることで最近あらためて重要だと思っているのは、ロードマップを立てるという考え方。この両立に極めてとても有効だなと希望を感じています(笑)
両立させるのは難しいですが、成果責任も時間が経てばその質や量が増えていくことを期待したいじゃないですか。
個人の成長というスケールで見た時に、半年後にはこのくらいになっていると、きっとフロントでもバリバリ活躍できると考えられるなら、その時に生まれている成果のサイズも変わっているはずです。
成果責任と個人の成長を1本の軸の上で並べて考える、それを実現するのがロードマップというツールなんじゃないかと思います。
籔田:ロードマップを立てることと、それ通りやることは難しいですよね。でも確かにこの1年で、ロードマップとは何ぞやというところから始まって、組織で共通言語になりましたね。
さとりこ:プロダクトデザインという領域でこれをやっていると、スプリントという1週間ごとのサイクルがあるので、結構プロセスが型にできるところだと思います。短期的な成果責任を果たしてもらう中で、毎週そのタイミングが来るわけです。そこに向けて毎週再現性を持たせる、今週できた部分が来週もできていて、今できていない部分も1歩ずつできるようになっている状態を目指しています。
ウィークリーの再現性を持たせることが個人の成長につながると思って取り組んでいます。
籔田:マネジメントする上での再現性は永遠のテーマですよね。さとりこは今クォーターで再現性がテーマになっていますが、どの再現性を作るのが今一番難しいですか?
さとりこ:言語化や構造化など、自分が得意でやってきた方法になってしまい、特性や思考が異なる色々な人がわかりやすい型をつくることに苦労しています。
第5回放送分より
テーマ3:事業価値を最大化するためのデザインリソース配分はどう考える?
籔田:では続いては、事業価値を最大化するためのデザインリソース配分をどう考えていますか、というテーマです。
まずはデザインパートナーとして対クライアントに対してですね。クライアントの事業全体で見た時のデザインリソースの配分について、どんな風に考えながらマネジメントしていますか?
さとりこ:お客さんの体制やケイパビリティによって変わるので、難しいですが、
最初はやはり要求されたQCDで答えることが初手だと思っています。それに全力を注ぐ。その後、やっていくと見えてくる課題があります。
例えば、属人化していたり、プロダクト上、何を開発すべきかが見えていなくて自転車操業になっていたり。最初の要求に答える中で分かっていくことがある、ですかね。
籔田:まずそのステップがあるということですね。やらないと見えないことがたくさんありますからね。見えてきた課題に対して、追加でリソースを投入する以外に、まず自分はどういうことをしていますか?
さとりこ:やはり仕組みにすることが大きいですね。今やっていることをできるだけコンパクトにして、余剰でできることを増やす。その余剰で、アセットを作ったり、チケットをこなすだけでなく何をやるべきかから考えられるようになることを目指しています。
籔田:さとりこが今クォーターで取り組んでいる仕組み化へのトライですね。へいへいはどうですか?
へいへい:目の前のことをやり続けると、良くも悪くも工場みたいになってしまうところがあると思っていて、今回のテーマが事業価値を最大化するためのデザインリソース配分ですが、そもそも事業価値にデザインがどのように貢献できるのかをしっかり考える必要があると思っていますね。
例えば、法律で事業の意思決定の半分が決まるような専門的な領域だと、ユーザーの声というよりも違う角度からの価値貢献が求められるケースがあります。デザインの価値をどういう風に定義できるか、頭をはたらかせなければいけない部分だと思います。
籔田:「顧客価値」はデザインだけが絶対要素ではないし、事業は顧客価値だけ、でも成り立たない。デザイン側の視点だけで物事を見がちになるのはなかなか、難しいところですね。
一方で、私たちはデザインパートナーではあるので、その視点で話してほしいと求められているのも事実です。特にAIが進化する今は、自分たちの意思や専門的な観点から「こうするべきだ」という仮説を持って伝えていけないと、自分たちの役割は縮小されますね。
テーマ4:メンバーそれぞれの強みをどう活かすマネジメントができる?
籔田:最後は、メンバーそれぞれの強みをどう活かすマネジメントができる?というテーマです。
実は事前にMGR等が「これが難しい」と言ってたテーマなんですが、強みを活かすマネジメントが難しいと思うところはどういうところですか?
さとりこ:前回も話したんですけど、自分と違う特性を持っている人に型を落とすことはできるけど、それがはまっているのか分からない。その人の強みを活かしてあげられていないかも?と思うことが多いです。
籔田:強みって抽象度が高いですが、どういう部分の強みと捉えていますか?
さとりこ:どういう思考方法が考えやすいかという特性を指しています。
へいへい:ぼくは役割責任の分解の辺りで色々自分の問題があるんですが、要求水準を満たせるラインを超えられるか否かというのは重要だと思います。
弱み・中・強みという幅があって、どのゾーンにいるかという捉え方をしています。明確な線があるというよりは、色々総合した結果このゾーンかもという感じです。
籔田:大前提として、マネジメントする上で、最終的には本人ががそれを目指す必要性を感じているかどうかが大事ですよね。
どんな考え方でマネジメントしたとしても、最終的にはその人がそれを目指す必要性を感じてるかどうかが大事。rootではみんな自分の能力よりは1個高いものを今挑戦してるっていう組織カルチャーがあるので、80点でやってる人もいれば、チャレンジしてるから30点とか40点でやってる人もいる。
こういう風になりたいとか、こういうことが実現できるデザイナーになりたいとかっていう次のステップがあるから、それに対するギャップを埋めていくことが挑戦そのものになりますよね。
なので、それをやりたいと思わなければ、もうそれは弱みになると私は思ってます。
その上で、ギャップを埋めるために、登り方はいくつもあると思います。
このハシゴのかけ方をいろんなバリエーションで持てるようになることが、マネージャーとして大事だけど難しい点なんだろうなと思います。
そもそも、ですが、なぜ2人はマネジメントをやりたいんですか?笑う
さとりこ:なにかを作れる価値の総量が増えると感じているからです。
色々な人に関わってもらうから難しいけれど、いろんな強みや弱みを持った人が集まったチームで価値を発揮してもらって、作った顧客価値が世の中に届いていく。自分がそれを高めるほど、いろんな人とはたらき、その価値が増えていくと思うからです。
へいへい:ぼくは、前提として誤解を恐れず言うと、デザインはそんなに難しいことではないと思っているんです。極論言うと誰でもできるのではと思っていたりします。誰でもできるようになったら、新しい眼鏡がみんな1つずつ増える。僕はその眼鏡を通して、みんなが新しい世界に可能性を感じている状態を見るのがすごく好きなんです。そういう状態を目指すためのマネジメントという考え方はすごく意味があると思っています。
籔田:めっちゃわかるし同意ですーー。デザインっていろんな職種の人がやっていることだと私も思います。デザイナーという名前になっていない人にもプロのデザイナーはいっぱいいますよね。いつも言いますが、過去や課題からだけではない、未来のありたい状態から描ける、デザインというハウをもっといろんな人が扱えるようになって、それができる状態を作っていくのは有意義なことだと思いますし、それを見ている姿がシンプルに好き、というのもとてもへいへいらしいなと思います。
リスナーからの声
籔田:Slack に届いた “生の声” をいくつかご紹介します!
🗣️「へいへいさんのテンアゲPoint、素敵!」
🗣️「AIが台頭する時代においては、課題解決だけではなく価値創造をどうやるかが問われる。自分たちの意思と専門性をもとに、クライアントが思いつかない領域をどう方向付けし、形にするかが大事だと感じました。」
や、それぞれのパートでリアルタイムに質問も上がるようになってきたラジオ。
籔田:さぁ、無事今回皆に聴いてもらえて何よりです〜笑
では、早いもので、そろそろ番組も終わりの時間となってきました。
rootラジオでの「問い」の時間は一旦ここまでですが、
明日以降、みんなが現場で色々な良い「問い」を持って、クライアントに向き合ったり、ステークホルダーに向き合ったりして欲しいなと思っております!
では、また来週この時間にお目にかかりたいと思います。さようなら!
おわりに
今回のrootラジオVol.3では、”マネジメント視点で考える事業価値に寄与するデザインとは?” シリーズとして、第4回、第5回の放送内容をまとめ、4つのテーマを通じて議論を深めました。
次回のラジオ記事でも、マネージャーの役割や責任から、顧客価値をどう創り、育んでいくのか、引いてはrootのビジネス価値をどう最大化していくのか?について事業マネジメント視点・ピープルマネジメント視点のそれぞれよりお届けしますので、ぜひお楽しみに!!
rootでは共にビジョン実現できる仲間を探しています!
私たちは、「Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜」をビジョンに、様々なフェーズのクライアントの事業と組織の成長を共に実現するデザインパートナーです。
クライアント支援の立場から、個社での実践経験から得られたノウハウや課題を、組織的にナレッジとして束ね、支援する各社へ還元し、デザインの活動領域を個人から組織・事業へ広げ定着を促すことで、持続的な事業の成長にデザインが活かされる組織を増やしていきたいと思われる方!
共に、Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜を実現していきましょう!
ぜひ、ご興味ある方、一度カジュアルにお話ししませんか?ご連絡お待ちしています!
👇カジュアル面談はこちら
カジュアル面談をご希望の方はこちらよりエントリーください。
👇rootの採用情報はこちら
Vision・Mission・Valueやカルチャー、はたらいているメンバーの紹介など、充実したコンテンツで採用情報をお届けしますので、ぜひ、ご覧くださいませ!
👇root公式Xはこちら
プロダクトデザインや組織づくり、事業成長に関する知見やイベントをはじめとしたお知らせを発信しています。
ぜひ、フォローをお願いします!
(公式X)
We are hiring !
デザインの実践を個から組織・事業に活かすことで、より良い世界の実現を目指し、
組織の右腕として事業価値を共に創り・育むデザインパートナーチームを共につくっていきませんか?
クライアント支援の立場から、事業価値づくりにデザインが活かされる組織を増やしていくことにご興味のある方、ぜひ一度お話ししましょう!