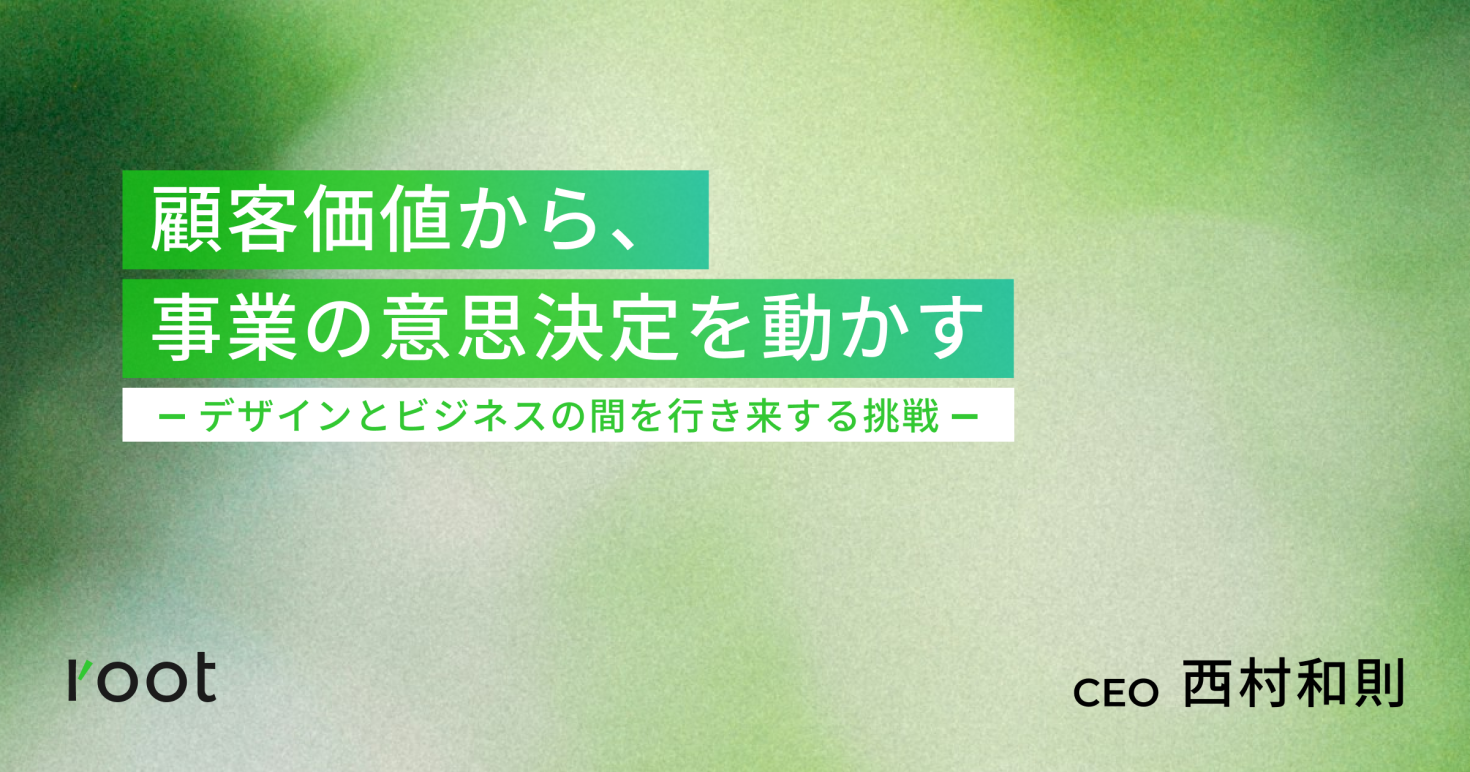- date
- 2025.08.25
プロダクトの「未来」を描き、デザイナーと共に「価値」を生み出すPdMの実践〜組織の右腕となるプロアクティブなデザインチームとは?rootラジオVol.6〜

こんにちは!root採用広報担当です。
私たちは「Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜」をビジョンに、組織の右腕として、共に事業価値を創り、育むデザインパートナーです。
rootのデザイン支援モデルは、クライアントワークを通じ支援する組織・事業に対して共に事業価値を創り、育むための支援体系を構築しています。
事業の立ち上がりや成長段階に関わることの多いrootだからこそ、事業の形がまだ定まっていないフェーズから、本来あるべき事業価値の創造を共に行い組織と事業の成長を目指しています。
目次
rootラジオとは?
社内でオンエアしているrootラジオを、ブログの連載企画として記事化しています。
冒頭で記載の通り、rootは、クライアント組織の右腕となるデザインパートナーとして、事業価値を創り・育んでいる中、 “rootラジオ”では、rootがクライアント組織の右腕となるデザインパートナーとして目指すことや、そのプロセスで起きるあれこれを、毎回トークテーマの中からゲスト(社内メンバー)とゆるく語り、その内容を社内で放送することで、それぞれに問いを立てていこうという企画になります。
また、rootはハイブリッド組織であり、現在は、オフィスでのコミュニケーションや関係値構築をセットで組織づくりを進めているフェーズです。
業務委託(rootでは、コラボレーターと呼んでいます)の方々はリモートのジョインが中心になるので、今社内でホットな情報や、組織の理解を深めてもらうためにも、ぜひ、聴いてもらればなと始めた放送でもあります。
ラジオで出てくる「問い」をぜひ、社内の皆が現場や日々の中で、引き続き考えたり、皆で話したり考えてほしいと考えています!
当面は3つのシリーズを考えており、直近はシリーズ3「組織の右腕となるプロアクティブなデザインチームとは?」について、お話ししていきます。
8個ほどあるトークテーマからルーレットを回し、その場で決まったテーマからお話ししていく企画になっています。
今回のゲスト紹介
今回は、ラジオ放送の第8回と9回の様子を記事にしていきます。
ゲストには、下期からコラボレーター(業務委託)としてジョインして下さっているPdMのたろうさん(※)を迎えお送りしました。
たろうさんは、現在フリーランスになられ、MBA取得のためスペインの大学院に在学中で、今回はラジオ初✨スペインからの生出演となりました!!
rootの組織づくり(サービスディベロップメント活動)にも色々とプロアクティブにご一緒いただき、rootの皆も大好き!リスペクト!な、たろうさんとお送りしたラジオ内容をお伝えしていきます。
小林 正和(コバヤシ マサカズ)
rootでは、プロダクトマネージャー(コラボレーター=業務委託)としてジョイン。
ニックネームは、たろうさん。
デザインコンサルティング企業でUI/UXコンサルタントを経験後、事業会社でアプリのUX改善のPM、PO、PdMを経験。プロダクトデザイン部門のグループマネージャーとしても従事。
現在はフリーランスとしてプロダクト開発支援をしつつ、MBA取得のため、スペインの大学院に在学中。rootには、デザインのアウトプットにとどまらず、自走できる組織設計まで支援できる点に共感しジョイン。toBのエンタープライズ企業において、新規事業開発を支援。PdMの経験を活かし、プロダクトに対するQCD担保全般を担い、方針検討からロードマップ策定、カスタマージャーニー設計から要件定義まで幅広く担当。
“デザインとビジネスを適切に融合させ、より価値の高いプロダクト・事業をつくっていける第一人者となりたい”と考えている。
(本ラジオのパーソナリティは、サービスディベロップメント兼HR・コーポレートセクションの管掌ジェネラルマネージャーである籔田が担当)
では、rootラジオレポート Vol.6はこちらです!
PdMの役割の変化、意思決定のコツ、チームビルディングなど、rootの実践を通じたリアルな問いや視点が詰まった内容になっていますので、ぜひ、ご覧ください!
放送内容
第8回放送分より
テーマ1:PdMの役割として、体験価値の創造は重要なアウトカムになってくるが、その先にあるデザイナーとの分掌や役割は?
籔田: 体験価値の創造は今までもPdMの役割でしたが、それがより重要になってきているという話があります。モノの価値だけではなく、体験で価値が生まれることのウエイトが増えてきた中で、PdMとデザイナーの役割ってどう変わっていくと思いますか?
たろう: そうですね、この体験価値の創造に対する重要度は確かに上がってきていると思っていて。簡単に誤解なく言えばパクれてしまう時代だからこそ、どれだけちゃんと体験価値に思いを込めたり、差別化ができるかがすごく重要だなと思っています。
私は 「タイムシェア」と「マインドシェア」という表現をよく使っていて、時間のかけ方と心のかけ方の話なんですけども、体験という意味で言うと、タイムシェアはあまり割けないけれど、マインドシェアはすごく大きくなっているのが今なのかなと。
籔田: タイムシェアとマインドシェア、なるほど!
たろう: AIを含めて色々なツールが出てきている中で、簡単にものがつくれるからこそ、何をつくるかを考えなきゃいけないことが多すぎて、PdMがパンクしちゃうというのは最近よくあるなと思っています。
やることが増えすぎて、PdMが体験価値に時間を割けないけど、体験価値が大事ということはみんな知っているから、マインドシェアは上がっているというギャップが生まれているんです。
なので、時間が割けない中で、外注するなり、パートナーと一緒にやるなり、タイムシェアが割けないところをどうデザイナーを含め介在していけるかが、役割分掌になるのかなと。体験価値を創っていくところにデザイナーがどれだけ入っていけるかが、ますます役割としては必須になってくると個人的には思っています!
体験って、提供価値をエンドユーザーの心のステップに落とし込んだものだと、解釈しています。流派ありますが(笑)
提供価値の設計はPdMもしくはビジネスオーナーがちゃんとした方がいいと思っていて。それを体験に落とし込む時の体験価値は、PdMがやることもあるし、UXデザイナーがやることもあったりするので、UXデザイナーがどんどんPdMの役割を染み出してやっていければ一番いいのかなと捉えています。
テーマ2:ロードマップを”あえて白地にしておく領域やセグメント”はありますか?またそれは、なぜですか?
たろう: 当たり前のことではあるのですが、短期と中長期といった時間軸で粒度を変えるようにしていますね。1年のロードマップだったら最初の3ヶ月はすごく密度濃く書くし、3ヶ月以降は割と大枠しか書かない。でも1年後のゴールだけはすごく明確にしておくんです。
大事なのはゴールを書いておくことと、3ヶ月経ってどうピボットできるか。うまくいくことは大体ないので(笑)
うまくいかなかったところは何か、それをアップデートしていくことが大事な観点かなと思っていて。そのためにそれ以降のところは一旦薄くしておくんです。
籔田: 時間軸以外で、この領域はあまり決めすぎないようにしている、みたいなものってありますか?
たろう: 強く意識しているのは、次のステップに行けたり、何かが決まるとはどういう状態かをロードマップに書くようにしています。誰にここでちゃんと合意を取ったり、承認が降りたら次に行けるのか、というのを結構入れています。
ロードマップで、企画とかデザインとかコーディングとかはよくあるんですけど、一番上に承認プロセスとか会議体を書かない人って結構多いんですよね。それだと進んでいるようで進んでいなかったり、結局手戻りが起こってスケジュールが破綻することが多いんです。
籔田: クライアントワークをしていると、ステークホルダーがどんどん増えていく中で、承認が曖昧になったりすることって結構ありますよね。
たろう: そうなんです!内部ではいいものを作っていてどんどんやっているけど、クライアントの担当者が上への承認を取れなくて全然進まないとかって、多分皆さんもあると思うんですけど。
クライアント側にも役割を与えるというか、「いいものはみんなでつくっているけど、承認だけはあなたしかできないから本当にお願いします」というメッセージもロードマップに込められるかどうか、って結構大事だったりします。
第9回放送分より
テーマ3:PdMってどんな人がマッチしていると思う?
籔田: PdMってどんな人がマッチしていると思いますか?これまでの経験も含めて教えてください!
たろう: 2つあるかなと思っていて。
1つ目は、未来志向というか、成長していったらいいなというものに思いを向けられる人、興味がある人がすごく大事だなと思っています。
PdMって要件を決めたりする時間が多いので、システムに明るかったり、要件定義に明るい人が良いと言う人もいるんですけど、どちらかというとそれだと目の前のものづくりに偏ってしまう。
プロダクトがどうあるべきか、事業がどう成長していくべきかに興味がある人の方が、長期的にはうまくいくことが多いと思います。
籔田: プロダクトマネージャーだから、「プロダクトの未来を考えて旗を立てること」が、1番の仕事ですよね。
たろう: たしかに、たしかに!今聞いてて思ったのですが、マネージャーという言葉でも同じような議論があって、平凡(・・っていう表現が正しいかわからないですが)なマネージャーは管理をしたり、目先のタスクはできるけど、その先の検討ができない。
組織をどうしていけるかを思考できるのが強いマネージャーだとした時に、プロダクトマネージャーも同様の考え方だなと思いました。
籔田:どんなマネージャーでもそうですよね。日本は、マネジメントって管理すること、っていう概念が敷かれてしまっている。ちゃんとありたい未来を描けて、そこに攻めていけるかがとても大事で。
では、2つ目はなんでしょう?
たろう:2つ目は、シンプルに意思決定ができる人ですね。特に不確実な状況がどうしても多いので。
分からない中で、今ある中での仮説や情報を基に、一旦意思決定をするって、結構勇気がいることなので、そこはすごく大事なポイントかなと思います。
籔田: なるほど、ありがとうございます。
ここで、リスナーから質問が来ています。「PdMとして良い意思決定を定義するとしたらどのようなものだと思いますか?」
たろう: 1つ目はちゃんと理由が語れること。なんでこの意思決定をしたかの理由がちゃんとセットで言えていると、納得されなくても「それで行くんだ」と思えるんです。
2つ目は、PDCAが回ること。絶対に間違った意思決定もしてしまうシーンはあるので、その意思決定に対して、何だったら良くて、何だったら悪いかが定義されていて、悪かったなら振り返って次に繋げられれば、それはいい意思決定と捉えることができます!
籔田:判断だけではなく、決断する覚悟ってそういうことですよね。最初から絶対解なんてないのが前提で、ある種楽観さももって、色々な変数の中で時に謝ったりすること、それも含めて軌道修正することが前提で、意思決定するってことだなって思いますよね。
テーマ4:プロダクトづくりにおいて「熱狂」を組織内でどう醸成したり浸透させてきましたか?
たろう: 私の場合はエンタープライズの大きめのプロダクトを持っていたことが多かったので、PdMも何人かいたりして、それぞれの興味関心が多様だったんです。
そこで私がやっていたのは、その人の好きや興味みたいなところをプロダクトに対してアジャストするということでした。
例えば、プロダクトにそんなに興味はないけど、分析がすごく好きな人とかいるんですよ。
その分析に注力させてあげるようにすると、最初の興味関心とプロダクトの一側面を繋ぐことで、楽しくなってきたら後は広がっていくんです。
籔田: その熱さがどこにあるかを、どこにどう繋げていくかってことですね。
たろう: そうです!一緒の組織にいるメンバーの興味に寄り添っていくことをすごく大事にしていました。
そこを刺激しないと、タスクだけして終わるみたいなことになりがちなので。停滞している人って、トリガーが引かれていないだけだと思っていて。ルンルンになったらなんでもやれちゃうのはみんなそうだと思うんです!(笑)
籔田: 「ルンルンになったらなんでもやれちゃう」、名言ですね!笑 セルフマネジメントでも自分のご機嫌は自分でとるって大事ですしね。
たろう: ルンルン状態に持っていくのが大事ですよね。無理やりルンルンにするのもありで、例えば「学校から家まで10分で帰れたら、今日ルンルンや」って言って強制的にするとか。自分のルンルンスイッチを決めるのもありかもしれません!
籔田: ですよね。しごとやタスクも割と、スイッチ入れれるものからしてテンションあげて、難しいものをその延長でやっていく、みたいなのは割とやっている人多いかもですね。これ、ルンルンスイッチですね。笑
おまけ編
異なるプロジェクトのアサインメンバー同士だと、質問できる機会も皆少ないため、ルーレットで今回当たらなかった他テーマについても追加でいくつかの質問をしてみました!
Q:rootでPdMというロールから価値提供することの意味やおもしろさとは?
たろう: デザイン・組織の両面から入っていける点ですね。デザインを思考する上で、体験やユーザーニーズを共に考えプロダクト検討ができるし、それを受け止める組織側がどうあるべきかを考えながら共創できる点がとてもユニークです。
Q:クライアントワークの楽しさ・興味深さってどういうところに感じているか?
たろう: クライアントワークとして俯瞰してプロダクトを見れるため、本質思考で考えやすい点が興味深いです。
詳細はクライアント側が熟知しているからこそ、より本質的な提案がどうできるかと思考する割合が高いのが面白いなと感じます。あとはプロジェクトも複数持つので、toBとtoC、SaaSやメディアなど、様々なプロダクトに触れて思考できるのはとても楽しいです!
リスナーからの声
🗣️「不確実な状況で材料が少ないとき、どんな軸で意思決定するのか?短期と長期で違いはあるのか?」といった質問や、
🗣️「たろうさんの言語化は実践に根ざしていて、試行錯誤の積み重ねが見える。とても納得感がある!」といった声。
🗣️「シビアな状況ほどゲーム化して楽しめる視点を持ち、メンバーを巻き込めるのが素敵だと思いました!」といった声。
が挙がり、それぞれのパートでリアルタイムに色々な声が上がっていました。
籔田:さぁ、無事今回皆に聴いてもらえて何よりです〜笑
では、早いもので、そろそろ番組も終わりの時間となってきました。
rootラジオでの「問い」の時間は一旦ここまでですが、
明日以降、みんなが現場で色々な良い「問い」を持って、クライアントに向き合ったり、ステークホルダーに向き合ったりして欲しいなと思っております!
では、また来週この時間にお目にかかりたいと思います。さようなら!
おわりに
今回のrootラジオVol.6では、”組織の右腕となるプロアクティブなデザインチームとは?”シリーズとして、第8回、第9回の放送内容をまとめ、4つのテーマを通じて議論を深めました。
PdMの視点から見た体験価値創造の重要性、意思決定のコツ、そして組織に「ルンルン」を生み出すチームビルディングまで、実践的な知見が詰まった内容となりました。
次回のラジオ記事でも、「組織の右腕となるプロアクティブなデザインチームとは?」シリーズをお届けします。
rootのメンバーをゲストに、プロアクティブなデザインパートナーとして、各ステークホルダーにどう向き合い、どんな体現やアクションを目指すのか?今回話題に上がったプロアクティブさ(主体性)の具体をさらに深掘りしていきますので、ぜひお楽しみに!!
rootでは共にビジョン実現できる仲間を探しています!
私たちは、「Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜」をビジョンに、様々なフェーズのクライアントの事業と組織の成長を共に実現するデザインパートナーです。
クライアント支援の立場から、個社での実践経験から得られたノウハウや課題を、組織的にナレッジとして束ね、支援する各社へ還元し、デザインの活動領域を個人から組織・事業へ広げ定着を促すことで、持続的な事業の成長にデザインが活かされる組織を増やしていきたいと思われる方!
共に、Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜を実現していきましょう!
ぜひ、ご興味ある方、一度カジュアルにお話ししませんか?ご連絡お待ちしています!
👇カジュアル面談はこちら
カジュアル面談をご希望の方はこちらよりエントリーください。
👇rootの採用情報はこちら
Vision・Mission・Valueやカルチャー、はたらいているメンバーの紹介など、充実したコンテンツで採用情報をお届けしますので、ぜひ、ご覧くださいませ!
👇root公式Xはこちら
プロダクトデザインや組織づくり、事業成長に関する知見やイベントをはじめとしたお知らせを発信しています。
ぜひ、フォローをお願いします!
(公式X)
We are hiring !
デザインの実践を個から組織・事業に活かすことで、より良い世界の実現を目指し、
組織の右腕として事業価値を共に創り・育むデザインパートナーチームを共につくっていきませんか?
クライアント支援の立場から、事業価値づくりにデザインが活かされる組織を増やしていくことにご興味のある方、ぜひ一度お話ししましょう!