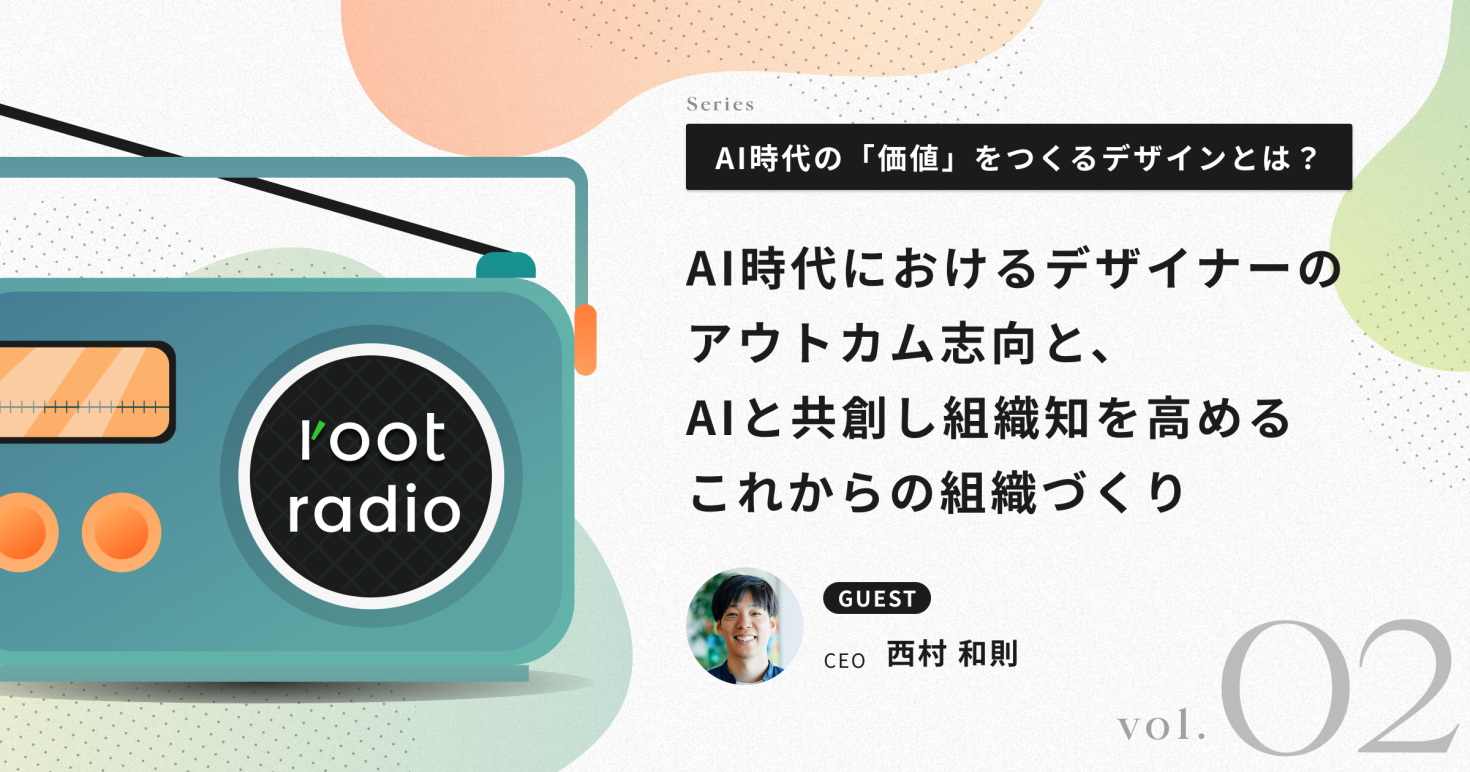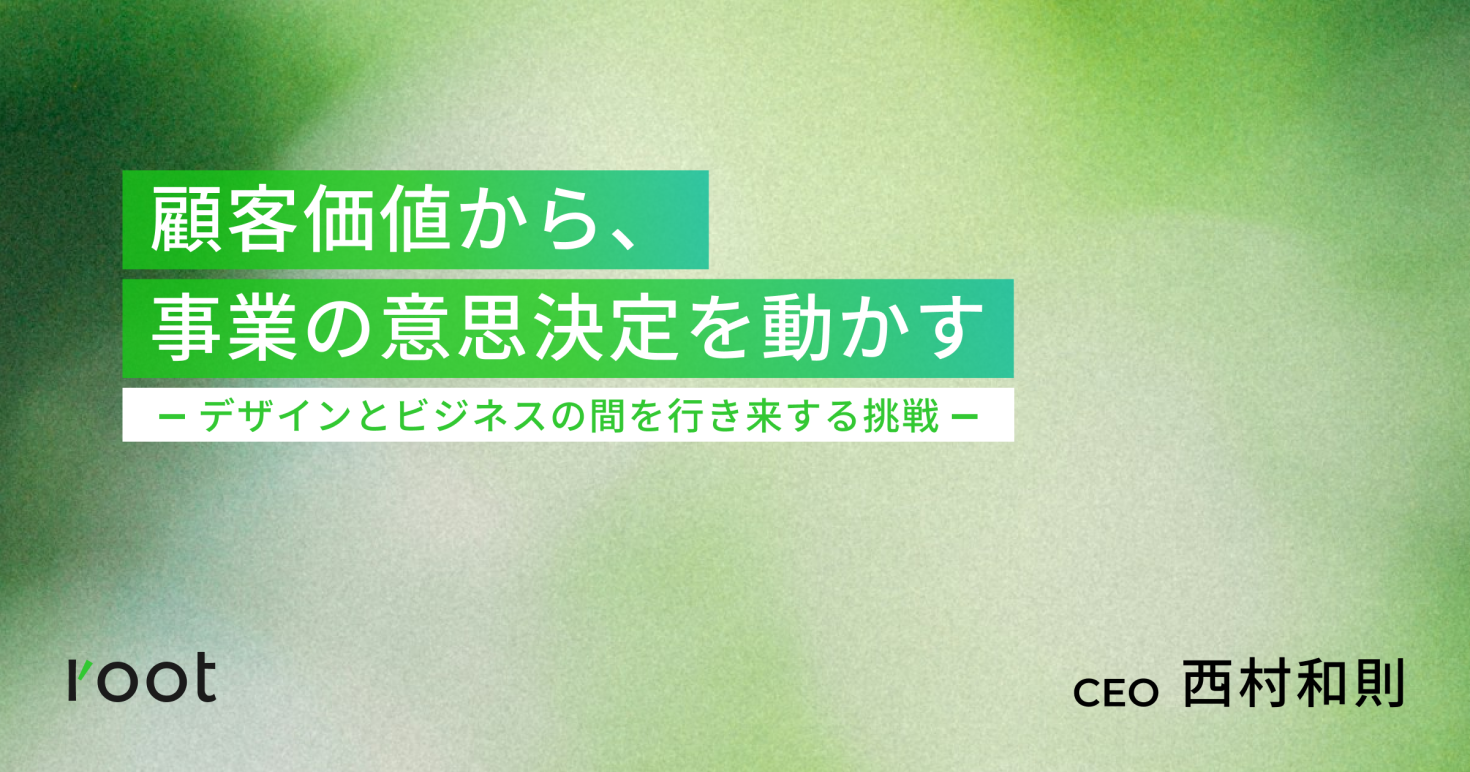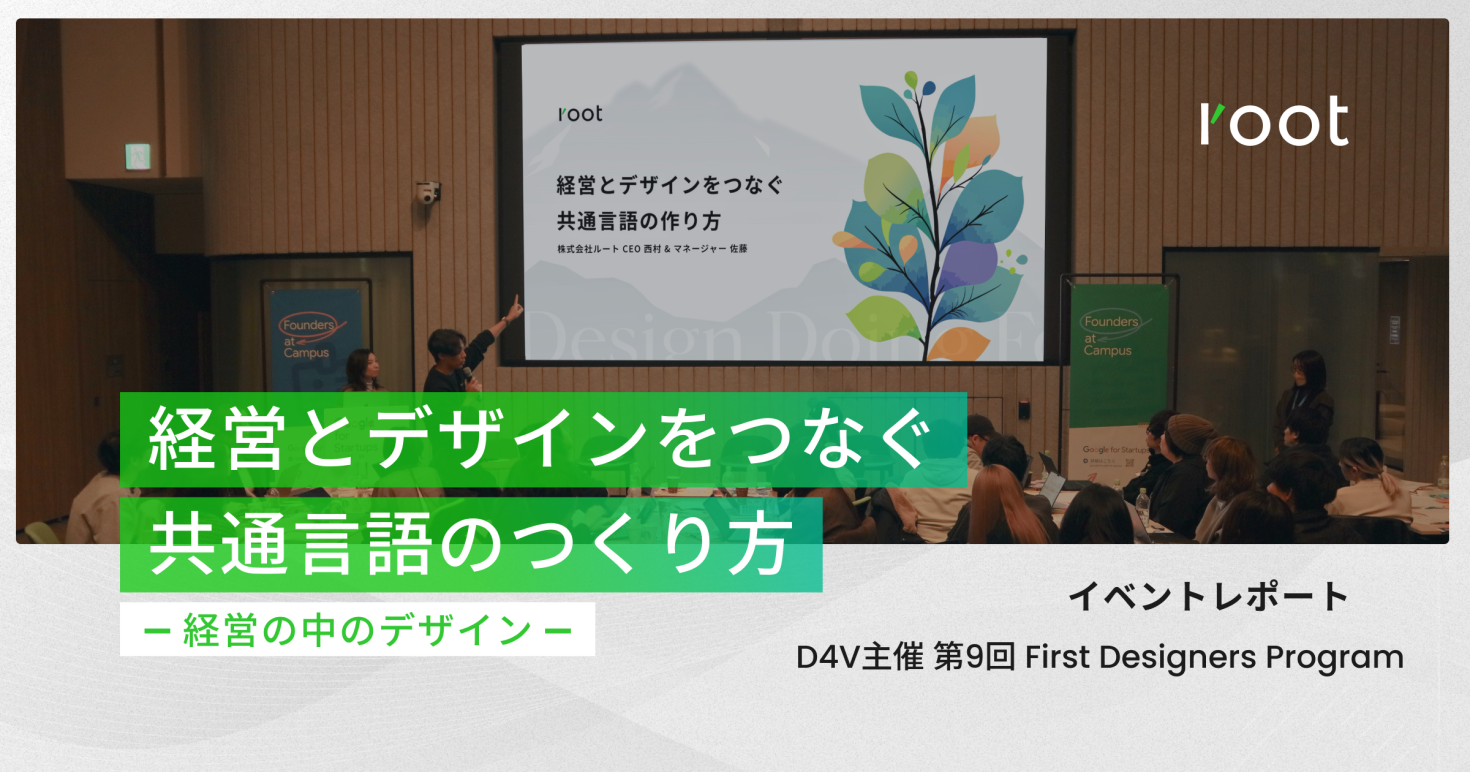- date
- 2025.10.16
デザインリーダーシップの初手!目標の本質と、裁量を広げる役割責任とキャリアの縦横〜組織の右腕となるプロアクティブなデザインチームとは?rootラジオレポートVol.8〜

こんにちは!root採用広報担当です。
私たちは「Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜」をビジョンに、組織の右腕として、共に事業価値を創り、育むデザインパートナーです。
rootは、デジタルプロダクト・ブランドマーケティング領域にて、クライアントの組織・事業に対して、継続的にデザイン支援をし、共に事業価値を創り、育む支援体系を構築しています。
私たちは、クライアント組織内のデザインチームや新規事業チームと共創し、組織に対して、事業立ち上げ〜成長フェーズにおける事業成長とデザイン体制構築に関するノウハウ支援 ・デザイン実行の支援をしたり、事業成長に応じた体制構築で、再現性のある新規事業チームの組成から持続的な組織づくりを支援しています。
また、創業前の構想段階から、立ち上げ・グロース・組織化と、幅広い事業ステージに応じたデザイン支援を行っており、スタートアップの創業からグロースまでの多様な知見を活かした、新規事業の成功確率の最大化や、持続的に事業を育てるために必要なプロセス、デザイン組織体制の立ち上げ、発展支援をしております。
また、ブログの最後にて、今月末に開催するイベント「事業の成果につながる目標設計とは?デザイン目標から考える、事業価値づくりの実践」の詳細およびイベントリンクを添付しています。
今回のrootラジオで話した内容を、より深く掘り下げる少人数の限定イベント(抽選制)となっていますので、ご興味のある方は、ぜひブログをご覧いただいた後にご応募ください!
目次
rootラジオとは?
社内でオンエアしているrootラジオを、ブログの連載企画として記事化しています。
冒頭で記載の通り、rootは、クライアント組織の右腕となるデザインパートナーとして、事業価値を創り・育んでいる中、
“rootラジオ”では、rootがクライアント組織の右腕となるデザインパートナーとして目指すことや、そのプロセスで起きるあれこれを、毎回トークテーマの中をもとにゲスト(社内メンバー)とゆるく語り、その内容を社内で放送することで、それぞれに問いを立てていこうという企画になります。
ラジオで出てくる「問い」をぜひ、社内の皆が現場や日々の中で、引き続き考えたり、皆で話したり考えてほしいと考えています!
今回の記事は、これからリードデザイナーやデザインマネージャーを目指す中で、デザイナーとしてのキャリアに停滞感を感じている方、そして事業成長にデザインがどう貢献できるか模索している方に向けてお届けします。 「目標がない」と感じているデザイナーの方、「デザイン目標をどう立てればいいか分からない」という次期マネージャー候補の方、「縦のキャリアと横のキャリアの違いがピンとこない」という方にとって、実際の現場で起きている議論や気づきを通じて、明日からの実践に活かせるヒントが見つかれば幸いです。
今回のゲスト紹介
今回は、ラジオ放送の第12回と第13回の様子をまとめて記事にしていきます。
第12回のゲストには、いつもパーソナリティーのGMの籔田、第13回には、同じく籔田とリードデザイナーのむーを迎え、パーソナリティは、本ラジオ初!マネージャーのさとりこが担当し、お送りしました。
<ゲスト>
籔田:籔田 麻美(やぶた あさみ) /ゼネラルマネージャー
メガベンチャー子会社からミドル・スタートアップベンチャーのHRの立ち上げ・責任者に従事。
現在は独立し、複数社のHR領域の支援をしている。“選択肢を増やし、365日ワクワク生きられる世界”をつくることが個人のビジョンであり、デザインという未来を描く手段を通じて、事業や組織をより良くしていくというrootのビジョンとの重なりから、2020年よりジョイン。
現在は、rootのサービスづくりそのものとなるデザイン組織づくりとしてサービスディベロップメントプロジェクトを管掌し、ゼネラルマネージャーとして執行責任者を務めている。
むー:今村翔也 (いまむら しょうや)/プロダクトデザイナー
工学部デザイン科を卒業後、事業会社でインバウンド観光事業やスマホ向けカーナビアプリのプロダクトデザインを担当。
人々の豊かな暮らしをサポートすることで、モノ・コトづくりに携わる人とそれを必要とする人が、より幸せな状態を生み出したい、というビジョンを実現するために、より社会に提供できる価値を大きくしたいと考え、rootに2024年6月に入社。
主に、サイバーセキュリティや製造業向けのSaaSサービスを担当。チームでの品質担保と再現性を作ることをミッションに、リードデザイナーとしてデザイン制作とディレクションを担当。
また、社内の組織づくりでは、社内デザイナー育成プロジェクトのオーナーを務めている。
<パーソナリティ>
さとりこ:佐藤 理子(さとう りこ)/マネージャー
新卒でSIerに入社。よりユーザーに近い領域でのプロダクト開発に関心を持ち、2021年にrootに入社。現在は、マネージャーとして、rootの事業・人材マネジメントの責任をもち、また各プロジェクトでのデザインマネージャーとしては、主に企業向けサービスの支援に従事し、デザインのQCDSに責任をもち、デザイン浸透度を高めることに伴走中。
個人と組織のビジョンの重なりで、ワクワク生きられる人やチームを最大化させていきたいと考えている。
では、rootラジオレポート Vol.8はこちらです!
「デザイナーによる、目標に対するよくある誤解」「デザイナーのキャリアを考える上で必要な「役割責任の縦と横の概念」」「縦の裁量を広げるために、デザイナーがやるべきこと」など、 rootの実践を通じたリアルな問いや視点が詰まった内容になっていますので、ぜひ、ご覧ください!
放送内容
第12回放送分より
テーマ1:デザイナーによる、目標に対するよくある誤解
さとりこ: 今回、はじめてパーソナリティを務めます、さとりこです。よろしくお願いします!
それではDesignshipの直前スペシャルということで、デザインリーダーシップを高めていく上で、デザイナーやデザイン市場でのギャップや現場の課題について今日は、話していきたいと思います。
※Designshipは、“広がりすぎたデザインを、接続する。” がコンセプト。
最前線のデザインを学び、第一線のデザイナーと語り合う、デザインの祭典で、
今年は10/11・12に渡り開催され、様々な業界から様々なデザインに携わる2,000名以上の方々が、東京ミッドタウンに集結しました。
今回は、デザイン組織において設定されるべき目標が明瞭ではなかったり、その上で日々アウトプットになりがちなデザイナーの課題から、「目標」についてスコープして話していければと思います。
多くのデザイナー、デザイン組織とお仕事をする、また知り合っていく中で、デザイナーが企業の目標の構造に対しての理解が薄い点があると思っています。
まず、籔田さんからこの目標の構造について説明してもらいたいです!
籔田: でた、粒度が大きいなー!(笑) んー、そうですね。会社というのはボランティアではないので、事業活動を通じて利益を生み出し、その利益を再分配して持続可能な課題解決や価値創出をする活動体ですね。その事業価値を、時間軸と優先度、組織での分掌、この要素から、どう創っていくかの計画を立て推進する。その計画が目指す到達点が、目標として設定されます。スタートアップや変化の速い組織の中でも、これがない、というのはありえないです。そのスパンが短く更新されるだけの話であって、経営陣は、必ずその指標を置いています。でなければ、優先度が決められず今日、明日することが決められないからです。
さとりこ: なるほど。いつまでにという時間軸と、何を達成するのかが明確になっているということがポイントですね。
籔田: はい。KGIとKPIという概念も重要ですね。KGIはゴールのGです。
例えば、会社全体で考えると、例えば今期の会社のゴールがある。そのゴールを達成するために、各部署がマイルストーンとして立てる中間指標がKPIです。会社全体のKGIに対して、部署レベルで言うとKPIになるんです。KGIとKPIは、階層によって入れ替わる相対概念なので、部門内では、KPIをさらに分解し、自分たちの「KGI」として扱う形にもなり得ます。
さとりこ: rootのチームだと、お客さんのところに入ることが多いので、その場合はKGIがプロダクトの目標になるという感じですか?
籔田: そうですね、組織構造や目標の持たせ方をどう運用しているかによって変わるため絶対とは言えないですが、概ねプロダクトチームとしてもっているKGIがあるはずです。
そして、その先には、先に説明した構造で全社としてのそもそものKGIがあり、そこからドリルダウンされています。
さとりこ: 役割・責任をまず理解しましょうとか、組織構造を理解しましょうというのは、こういうところに効いてくるということなんですね。
籔田: そうですね。それがわからないと自分の目標=KPIがどういったKGI達成のための中間指標なのかがわからないはずです。KPIという中間指標である以上、それは何のためのマイルストーンなのか?がわかっていないと、受け身になってしまったり、指示がころころ変わるみたいな認識になったりするんですよね。この概念を理解できると、より上位の役割を取りに行きやすいですよね。
クライアントワークでは、クライアント、例えばPdMのもっている役割責任、目標が何かをわからないと、価値提供できないので、ここは事業会社よりわかりやすさがあります。
さとりこ: では、次はデザイナーがよく陥る誤解について話していきましょう。まず1つ目がデザイナーがよく主張する「目標がない」と思っている問題。ルートでも過去そんなことを言ってた時代もありましたよね。
籔田: そうですね、本質的にはそれはありえないんです!(笑)先ほどお伝えした通り、会社という活動体は必ず目標があって、その目標のために人がアサインされているんです。目標なくやるべきことというのは絶対にないというのが前提です。
さとりこ: なるほど。目標がないのではなく、見えていないだけということですね。
籔田:見えてないというよりは、 厳密にいうと、ゴールはあるけどもその達成のための中間指標でありKPIを、ある領域においては、言語化していない、という状況が発生している。この領域がデザインという領域であるということですね。
また、組織というのはいろんなステークホルダーが混ざり合う中で、すべてを目標から具体的に落とすわけではないので、結果的に関係のないことのように思ってしまい、何かをしているということはあります。他にも、マイルストーンを達成するために必要な業務を、横断的にルーチンやフローにし、体系化されている業務があるかと思います。効率的に組織を運営するために体系化されルーチン化されています。そういう場合はどうしても見えづらく、わかりづらくさせてしまう要因ですね。ただ、それらも何かしらの事業のゴールから設定されているアクションなはずなんです。それをあるはずという前提に立って、それを確認しにいくということを、まず1人1人がそれを意識するということからしか、初手は始まらないと思います。
さとりこ: デザインマネージャーがみんな立てていけたらいいんですが、今は立てられないマネージャーもたくさんいるという市場になってしまっているので、アクションする側も「ない」のではなく、自分に見えてないだけだと思って、目標を理解するような活動が必要ですね。
籔田: そうですね。市場構造としては、デザインマネージャーのもう1段上のレイヤーがそれを落とせないことも課題ですし、デザインマネージャー陣も同じくですね。しっかりとそれを設定していくということを努めていかなければならない、ということだと思います。
さとりこ: 2つ目の誤解は、デザインの目標を、デザインマネージャーが独自で自由に立てられると思っていること、ですね。
籔田: これ、発生しがちだって、さとりこもよく言っていますね。先ほどの通り、会社における目標というのは、ピラミッド組織であれば、経営計画や事業計画、その目標がKGIとしてあり、そこから各部門でのKPIがあるという構造です。
端的に言えば、勝手にKGIを立ててはいけないんです。
1つ上の階層の目標を実現するための中間指標を目標として設定しなければ、会社全体で目指していく目標をチームで分解できていることになりません。
プロダクトチームの目標を理解して、デザインチームはそれに対するKPIを立てていくことがまずは必要です。デザイナーだけKPIがないという状況だったところに、デザイナーのKPIを立てていくということが必要であるということです。
さとりこ:確かにその通りですね。
3つ目は、全ての目標に対してデザインで貢献できるわけではない、だからこそどう目標を設定するかということですね。
籔田: そうですね。例えば商品バリエーションを増やすというKPIに対しては、UXでは解決できないですよね。でも、購買体験の改善なら解決できる。スコープをちゃんとできれば、目標が立てられるということ。KGIから考えるともっと色々できることがあっても、デザインだとKPIはどこまでなのかというのがあります。かつ、それをQ、半期、という時間軸で区切った時に、どこまでできるのかです。うちはクライアントワークなので、これをお客さんと握るということが、KPIを立てることと同じだと思うんです。
あとは、次のステップになりますが、別にデザインという領域だけではなく、目標は指標であるということの解像度を上げ、その状態を達成しているといえるには、対象者、ユーザーやクライアント、ターゲットがどうなっているか、というあるべき状態を定義できているか、が重要です。これを理解できずに目標設定しちゃっているケースが結構あるのが目標設定の罠。ここを、今度のイベントでも話していけるといいなと思います!
さとりこ:顧客体験を改善してコミットするのはここ、というスコーピングがちゃんとできれば、その目標が立てられるということなんだなというのがすごくわかりやすい例でした。イベントでは、次のステップもぜひ、咀嚼したいですね!
第13回放送分より
テーマ1:デザイナーのキャリアを考える上で必要な「縦と横の概念」
さとりこ:今回はゲストにリードデザイナーの、むーと、前回から引き続き特別に籔田さんをお呼びしています。
むー:よろしくお願いします!初登場で、ちょっと緊張していますが色々話していければと思います!
さとりこ:それでは「デザイナーのキャリアを考える上で必要な縦と横の概念」についてです。籔田さん、この縦横についてご説明いただけますか?
籔田: でた、また粗い振り方!笑 えーっと簡単に言うと、さとりこがよくメンバーにも言っていますが、縦は解決できる問題の大きさ、横は解決できる問題の種類です。横に広がって、1段縦に上がって、また横に広げて上がるという、ジグザグに上がっていくイメージですね。
さとりこ:むーはどういう風に捉えてますか?
むー: 自分のイメージだと、具体的に言えば、横に広がるというのは、プロダクトをリリースするにあたって、エンジニアリングや営業など職種をまたいでやるべきことが横に増えているというイメージです。縦は役割の責任が広がっていくところで、情報設計、体験設計、要件定義というように、裁量幅のレイヤーが上がっていくことだと思います。
籔田: そうですね。それも1つの具体ですね。同じように、職種という単位だけでなく、同じプロダクトデザイナーの中でも、どんな事業領域をしているか、どんなクライアントを支援しているかによって任されている範囲が違います。それが横という概念です。
さとりこ: デザイナーにとって縦横の概念がないことが問題で、横ばかり増えていって縦が増えていないから、キャリアとして挑戦している実感が得られないということですね。
籔田: そうですね。市場として発生しているなと。よく、うちでも話題になりますね。高さを持てるということは、自分1人で問題解決を持って解決できる範囲が大きくなるという話なんです。裁量というやつですね。いろいろ手をつけているけど、どれも最後まで遂行できないとなると、QCDSを担保できる範囲がどこなのかということになってしまいます。そして、縦が高くならないと、「責任」が「大きく」なっていかない。責任が大きくならないことには、「視座」が上がりません。これでは事業を動かすことができるデザイナーが増えない。市場構造の課題にもつながっています。
テーマ2:縦の裁量を広げるために、デザイナーがやるべきこと
さとりこ: では、最後のテーマです。縦の裁量を広げていくためにデザイナーがやるべきことについて、むーはどう考えていますか?
むー: 組織においては、自分より上に人がいるわけですよね。例えばデザインマネージャーがやっている仕事の中で、次に自分が挑戦すべき仕事を見つけて、それができるようになるためにアクションを取っていくことが初手は重要だと思います。
籔田: そうですね。最初はレビューをもらわないでこの仕事をやれるようになることがファーストステップですね。
むー: そうです!レビューの回数を少なくしていくところでも、役割・責任の裁量をもらっていける部分になるかなと思います。まず1つ上の人の、自分が1番近しい仕事をどんどんやっていく。これがやるべきことなのかなと理解しました。
籔田: 今持っている裁量を広げること、高さを上げていくことは、むーが言うように、完遂できてないものに対して、ちゃんと完遂できるようになるためのマイルストーンを設定できているか。そのマイルストーンを1つ1つ達成していくためには、承認やレビューが必要なものにちゃんと説明提案をすること。それを繰り返す中で、クオリティが問題ないと判断されれば「もう、承認通さずでいいので、やっといて」と言われるようになる。時間軸も同じで、何をいつまでにどれくらいできるかで、任すものの高さは変わります。これが役割・責任を渡されたということになります。
さとりこ: そうですね。自分の役割責任に対して、それを大きくするために、上司や先輩とのギャップを理解し、自分でロードマップを立てる人が成長していくんですよね。まず間にロードマップを立てるということ、これをやっていければなと思います!
リスナーからの声
🗣️ 「1つ上の目標からデザインの目標を立てる時の、スコープの仕方においてまだ解像度が粗いので、今Qはそこにトライしていきたいと思います」
🗣️ 「クライアントワークだと相手がいるから縦の概念が理解しやすいですね。クライアント側にも役職や責任範囲があって、自分がどのレイヤーの人に対して、何を提供できているかがわかりやすいですし、相手の目標や役割責任を確認しにいく構造になる。成長が実感できますね」
おわりに
今回のrootラジオVol.8では、”組織の右腕となるプロアクティブなデザインチーム” シリーズとして、第12回、第13回の放送内容をまとめ、3つのテーマを通じて議論を深めました。
「目標がない」と感じていたデザイナーの方には、企業活動において目標は必ず存在し、それを認識し接続する方法があるという新たな視点を、「デザイン目標をどう立てればいいか」と悩む次期マネージャー候補の方には、KGI・KPIの構造理解とスコーピングの重要性を、
そして「縦と横のキャリア」に迷う方には、具体的な成長ステップをお伝えできたのではないでしょうか。
これらの気づきが、明日からの皆さまの実践において、デザインで事業価値をつくり出していくための第一歩となれば幸いです。
次回のラジオ記事でも、「組織の右腕となるプロアクティブなデザインチームとは?」シリーズをお届けします。
rootのメンバーをゲストに、プロアクティブなデザインパートナーとして、各ステークホルダーにどう向き合い、どんな体現やアクションを目指すのか?
今回話題に上がったプロアクティブさ(主体性)の具体をさらに深掘りしていきますので、ぜひお楽しみに!!
事業を動かすデザイナーとして必要なデザイン目標やロードマップを立てるための実践!アフターイベントのご案内
rootでは、 Designshipのアフターイベントとして、Designshipの登壇や、今回のrootラジオで話した内容を、より深く掘り下げる少人数の限定イベント(抽選制)を開催します。
「事業の成果につながる目標設計とは?デザイン目標から考える、事業価値づくりの実践」と題して、
デザイナーが事業価値を生み出すための目標設計の方法やアプローチについて、実践的な学びを共有する場となります。定員10名程度の抽選制で、参加者同士にてワークショップも実施予定です。
以下イベント詳細です👇👇
・イベントページ:https://connpass.com/event/371985/
・日時:10/31(金) 19:00〜
・場所:rootオフィス(Quest虎ノ門)
・登壇者:CEO 西村、GM 籔田
今回の内容に共感いただいた方、実践してみたがうまくいかないという方は、ぜひご応募をお待ちしています!
rootでは共にビジョン実現できる仲間を探しています!
私たちは、「Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜」をビジョンに、様々なフェーズのクライアントの事業と組織の成長を共に実現するデザインパートナーです。
クライアント支援の立場から、個社での実践経験から得られたノウハウや課題を、組織的にナレッジとして束ね、支援する各社へ還元し、デザインの活動領域を個人から組織・事業へ広げ定着を促すことで、持続的な事業の成長にデザインが活かされる組織を増やしていきたいと思われる方!
共に、Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜を実現していきましょう!
ぜひ、ご興味ある方、一度カジュアルにお話ししませんか?ご連絡お待ちしています!
👇カジュアル面談はこちら
カジュアル面談をご希望の方はこちらよりエントリーください。
👇rootの採用情報はこちら
Vision・Mission・Valueやカルチャー、はたらいているメンバーの紹介など、充実したコンテンツで採用情報をお届けしますので、ぜひ、ご覧くださいませ!
👇root公式Xはこちら
プロダクトデザインや組織づくり、事業成長に関する知見やイベントをはじめとしたお知らせを発信しています。
ぜひ、フォローをお願いします!
(公式X)
We are hiring !
デザインの実践を個から組織・事業に活かすことで、より良い世界の実現を目指し、
組織の右腕として事業価値を共に創り・育むデザインパートナーチームを共につくっていきませんか?
クライアント支援の立場から、事業価値づくりにデザインが活かされる組織を増やしていくことにご興味のある方、ぜひ一度お話ししましょう!